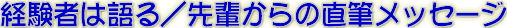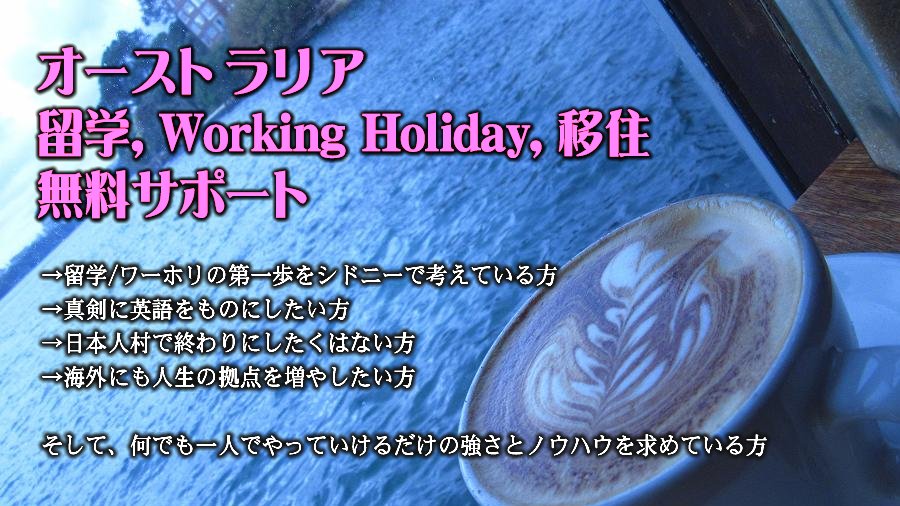◆旅の再開
飛行機に乗って向かった先はマレーシアだ。
マレーシアを5日間旅して、その後オーストラリアへ2年目のワーホリに向かう。理由は単純で、マレーシアに行ってみたかったからだ。それにオーストラリア2年目のワーホリはただ漠然とダーウィンと心に決めており、東南アジアとダーウィンはわりと近隣だということもある。
到着したKL(クアラルンプール)の埃っぽい空気は、早速異国情緒を感じさせるものだった。
そして翌日向かったペナンはKLより更に埃っぽい道にこじんまりとした店が軒を連ねていて、東南アジア独特の趣を感じた。昭和の屋台をも思わせる、どこか懐かしい風景だ。
湿度が高く、息苦しい熱帯気候の快適とは程遠い生活環境、それにお世辞にも衛生的とはいえないような店で、地元の人々に混じってローカルフードを食す。こういった瞬間、私の心は躍動し、エネルギーがみなぎってくるのを感じた。
ペナンはフード天国と言われているだけあり、屋台やそこら辺の店で何を食べてもおいしかった。まず、ペナンラクサだ。シンガポール発祥のラクサカレーとは全く別の食べ物で、ペナンラクサのスープは魚介の出汁がきいた透明のスープで、少し甘酸っぱいのが特徴だ。Char Koay Teowという、オーストラリアでも時々見かける、米粉でできたきしめんのような平たい麺とエビのフライドヌードルも絶品だった。鉄板の上で程よく焦げたエビの匂いだけでも、胃袋が半分満たされた気持ちになる。
ペナンの好きなところは、屋台で働く人達ひとりひとりに顔がある、単なるビジネスではなくて生活しているんだということをひしひしと感じさせてくれるところだ。屋台で注文する時、英語がなかなか通じない場面が何度かあったが、代わりにマレー語で店員に注文を伝えてくれる親切な客に助けられた。
初めて訪れた国で、こんなにも親しみがあって懐かしい感じがする場所は初めてだった。
夜は宿の窓から、夜市の屋台の明かりがもれてきて、なぜかそれが私を安心させた。そして朝には野菜を切る音や、食器を準備している音が聞こえる。粛々と朝市の準備が整っていくのを感じ、一種の安らぎを覚えた。
宿の窓の外には、朝市で始まり、夜市で終わるというペナンの1日が展開されていた。
Malaccaは早々と切り上げることになり、その翌日には再びバスに乗ること3時間。
PASAR SENIというKLの中心街にある駅に到着した。KLの町は想像していた通り、高層ビルが立ち並ぶアジアの都会だった。ホテルにチェックインし、荷物を置いてすぐに町へと繰り出す。
イスラム教のモスクに興味があったので、近くにあるSultan Abdul Samal BLをめざす。寺院に到着すると、入口付近から地べたにゴザのような絨毯が敷かれ、水とコンテナーに入った食べ物が置かれていた。人がぞくぞくと集まってくる様子で、はるか遠くの方にはなにやら列をなしている。
近くにいたおじさんに、「これから何が始まるの?」と尋ねたところ、「ラマダン前夜の食事会だよ」と教えてくれた。「きみも一緒にどう?」と言ってくれたが、「私はイスラム教徒ではないので・・・」明日からもきっとご飯を目一杯食べるだろう私が、ラマダンという神聖な儀式に加わることはなんだか不謹慎な気がしたのだ。しかし、おじさんは「そんなこと問題ないよ」と笑顔で言ってくれた。
バリ風のアロハシャツを着ているそのオジサンは、やはりインドネシア人で、 口数は少ないけれど、その笑顔から良い人オーラが滲み出ている。
おじさんに促されるようにして私もゴザの上に座る。どうしてよいのか分からずキョロキョロしていると、そのおじさんは立ち上がり、しばらくしてから戻ってくると両手に料理が盛られた皿を持っていた。そしてその一皿を私に差し出してくれた。わざわざ列に並んで、私の分の料理も持ってきてくれたのだ。食事の間も、日本のことやインドネシアのことについて話した。この親切なおじさんとの出会いは、素敵なサプライズのように私の心を温かくした。
交通ルールも無いに等しい、喧しく動くカオス的なKLの街だが無類の温かさを感じる場所だった。それは人々の信仰心とも関係があるのだろうか。飛行機の中でそんなことを頭に巡らせながら、シンガポールを経由してダーウィンへ向かった。
◆ダーウィンに上陸
午前4時にダーウィンの空港に到着した。入国審査を終えて検疫ゲートをくぐろうとした時、職員に呼び止められる。滞在先の宿については着いてから考えようと思っていたので、入国審査カードに滞在先を書いておらず、それについて激しく詰問された。どうゆうことだ、ということらしい。全く下調べもしていなかった。住まいも仕事も未定というのが怪しい印象を与えたようである。
先のマレーシアでは、日本人というだけで入国審査カードを見せることすらなくゲートをくぐることができたこともあり油断していた。滞在先の宿は適当にどこかのバッパーの住所でも入力しておくべきだ。
後に、ダーウィンは東南アジアからの不法滞在者や中東からの避難民が多いということ、その避難民たちが生活するDetention center と呼ばれる施設があるということを知った。もっとも避難民の多くは船に乗って命がけの航海で、オーストラリアに渡ってくるそうだが。
そういえば1年前の今日は西オーストラリアの港町におり、ちょうどエビ釣り漁船に乗り込もうとしていたことを思い出す。
Mindiビーチへ向かう途中、そんなことを考えながら、車が多い道路の反対側へ渡るタイミングを伺っていると、小さな芝生の上で花火を着火させている若者の姿があった。しばしの沈黙の後、突然その花火が火の玉のように回転して、私をめがけて飛んできた。花火は私の足元をかすめて通過し、付近の芝生に着地していた。あまりに一瞬の出来事で、私は唖然としてしばらく目をパチパチさせていた。
ダーウィンに歓迎されているのか、いないのか。オーストラリアワーホリ中で最長滞在地となるダーウィンでの生活が幕を開ける。
シェアハウスに移るまでは、ダーウィン市内のYHAに滞在していた。
同室だった香港から来た学生と一緒に行った、Litchfield National Parkは、源泉掛け流しの滝によってできた、天然プールのような透き通った水の泉があちこちにあった。ヒヤリと冷たい水、どこまでも広がっていく中を泳ぐ快感。これを覚えたら、25mプールでは物足りなくなりそうだ。
その数日後、私はカカドゥ国立公園へ2泊3日のツアーに参加した。
思い出に残っていることといえば、トイレをひたすら我慢していたこと。テーマパークのアトラクションと化したクロコダイル見物。荒涼とした景色の中に突如現れる、遺跡のような巨大アリ塚。アル中気味の短気なガイドの男。
ツアー最終日は、そのガイドが一刻も早く帰路に着きたいというのが誰の目から見ても明らかで、4WDをブッ飛ばしてゴーゴーと進む。前方にノロノロと進む車がいようものなら罵声を浴びせていた。仕事終わりのビールが待ちきれなかったに違いない。
このツアーに参加して良かったことといえば、1日目の夜のBBQで食べたカンガルーの肉が予想以上においしかったことだ。
◆仕事について
2 0件のレジュメを配り歩いた翌日、1件面接にこぎつけることができ仕事をゲットした。市内のホテルのハウスキーピングだ。
肉体労働のため、始めこそきつかったが、日ごとに仕事のスピード感が増し、体もどんどん軽くなっていく。アスリートのような心持で臨むと、平坦な仕事内容であるハウスキーピングが楽しくなった。
慣れてくると、誰に頼まれるでもないのにやたらと重いものを持ちたがり、筋肉量が増えていく自己満足を味わっていた。また、久しぶりの安定した仕事は、日本でのそれとは違い何だか清々しいものを感じていた。
ハウスキーパー達の国籍の割合は台湾が大部分を占め、その他韓国、フランス、南米、そしてアボリジニーの中年女性もいた。
ダーウィンに支店がある、日系の石油・天然ガスの会社のファンクションが現在私が働いているホテルで行われる予定だという。そこで、日本人である私は多少のアドバンテージなのか、ファンクション中はウェイトレスとして働くことになった。メルボルンからわざわざ日本人シェフを呼び寄せ、シェフは重役達の細かな要望に応じていた。また、クルージングでの船上ランチが企画されたりと、重役達をもてなすことに、どこの国でも余念が無いものだ。
ファンクションも終わりに近づいた頃、マネージャーから、これからはホテル内にあるレストランで働かないかと誘われた。
こうして始まった、ホテル内にあるレストランでの仕事は午前3時が勤務開始時間だった。
なぜこんなに朝早いのかというと、このホテルには70人前後の建設関係の労働者が長期滞在おり、彼らは朝5時にホテルを出発するバスに乗って約1時間半離れた仕事場に向かうため、彼らの朝食が朝の4時に始まるのだった。そして通常の宿泊客の朝食が朝6時から11時までだ。また、朝10時からアルコール類が注文できるようになるため、週末はブラッディマリーを朝食代わりに注文している粋な客もいた。
ここでは本格的なコーヒーマシンがあることを知り、喜び勇んで練習に臨む。Youtubeで動画を見て独学したり、地味な研究を重なることで、何とかましな形になってきた。しかし一番効果があったのが、日本人バリスタの友達がくれたアドバイスだ。
ミルクを入れるジャグの角度は常に水平で、チップの先はジャグの側面から数センチのところに向けることによって渦が発生する。また、底面からも数センチのところに落ち着けると安定し大きな気泡ができにくく、均一の極めの細かい泡になる。その他に、よく言われる、「ミルクジャグに1秒以上触れないぐらいの熱さが、適温の65℃」やミルクがぶくぶくアブクのように波打っている状態は、泡立てる温度が強すぎるからツマミを調節して緩める、といったものだ。
これを境に、しょぼくれた味だった私のコーヒーに革命が起きた(と自負している)。なにより自分が満足できるコーヒーを、毎朝飲めるというのが一番嬉しい。
シェフから事前に、「今回の客はBoganだよ」と言われ、Bogan(教養が無く、素行の悪い人)というスラングを覚える。ついでにCashed up Bogan (教養が無く、素行が悪いが金だけはもっている人)という単語も。
この日、パーティーは夜の11時から開始された。
既にどこかで飲んできたのであろう、ほろ酔い状態の男女30名が到着。そして飲むわ、談笑の、ごくありふれたパーティーの光景。
深夜2時になりバラバラと人がはけてくる。
しかし数名のオヤジ達は話に花咲かせており、深夜3時をまわる。
更にはこの時間から、オヤジ達はエナジードリンクのレッドブルを浴びるように飲み始め、非常に迷惑なことにますます活気づいていった。
朝の4時、別の仲間が合流し、人数が増える。
終わりが見えない宴に限界を感じたマネージャーが「朝の5時には片づけをして、ここを閉めなければいけないから」と説明するも、酔っぱらったオヤジの一人が、「このマンションは俺が所有してるんだ!だから好きな時間までいるぞー」とかダダをこねだす始末。更にはストリッパーを5人呼んだから、もうじき到着するのだと、やや血走った虚ろな目をこちらに向けながら言った。
結局そのオヤジが、今回のパーティーの主催者でありこのホテルの経営者のボスに連絡を取り、このまま滞在する許可を取っていた。同時に私達には退出許可が出されたため、ようやくこの場を離れられるという安堵感でいっぱいになる。
そしてストリッパーを待つ酔っぱらったオヤジ達を残して、私達はほうほうの体で帰宅した。帰り際に100ドルのチップを手渡されたが、複雑な心境である。Cashed up Boganという単語の意味を身を持って知った一夜だった。
◆ダーウィンのアボリジニー達
バスの中で突然ひっくり返って倒れるアボリジニーに、何度か遭遇した。そして、酒を持ち込もうとして、乗車を拒否されているアボリジニーも。ズボンの尻ポケットから突き出たものが見えて、銃?!と一瞬慌てふためいたが、よく見るとそれは明らかにワインのボトルだった。このアボリジニーの男は、途中で駆け付けた警官によって、抱え込まれるようにしてバスを降りていった。
ある時は、宿泊客ではないアボリジニーの家族がYHAの中にどやどやと入ってきて、辺りは騒然となった。受付にいたスタッフの制止を振り切って、建物の奥まで入ってしまった。スタッフは訳を聞こうとするが、そのアボリジニー家族の言い分は支離滅裂でスタッフを困らせていた。
「彼らはアニマルだわ。そう思わない?」この言葉が同室だったオージーの若い女の子から発せられた時、一瞬耳を疑った。そしてなんともその返答に困った。確かに、ダーウィンに来てからアボリジニーの人達の想像以上のアグレッシブさには、衝撃を受けた。しかし、そもそも彼らは初めからアグレッシブな民族なのだったのだろうか。それとも、侵略・略奪された歴史の中で歪んでいったものなのだろうか。ニワトリが先かタマゴか。いや、しかしダーウィンより北にある、小さな離島から来たというアボリジニーの女性客は、とても気さくで穏やかな目をしていた。
◆ダーウィンでの生活
ダーウィンが乾期の真只中である7月の夕日は、特に優雅で美しかったと記憶している。乾期の間は毎週木曜日と日曜日に、ビーチ沿いでマーケットが開かれており、屋台やみやげもの屋が並ぶ。夕焼けを背景に、砂浜で遊ぶ子供、赤ん坊を抱いた夫婦、寄り添う家族が影絵を創りだしていた。そんな風景をぼんやり眺めながら、持参した冷蔵庫でギンギンに冷やしたビールを片手に屋台で買ったご飯を食べるのが楽しみだった。
また、夕暮れ時に始まる、ディジュリドゥ(アボリジニーの伝統楽器)とドラムのセッションは、圧倒的なグルーブ感だった。 そのリズムにのって、人々(主にアボリジニーの人達)は独特なダイナミックなダンスを踊る。よくみると、普通の人には真似できないような細かいバイブレー動きをしている者もおり、それは一種の儀式のようにも見えた。その儀式的なものの中の躍動感は、見るものを圧倒していた。
ダーウィン生活の細かなことを、卒業生専用の掲示板で教えてくださっていたので、ここに引用掲示します。
シェア
さてダーウィンに滞在していた約6ヶ月の間に、ダーウィンの中心地であるシティエリアの半径500メートル以内で、3回住まいを変わった。一発目のシェアハウスは、台湾人7人と中国人2人という構成で、この中国人というのがそこのオーナーと、その母親だ。彼女は皆にアンティ(オバちゃん)と呼ばれていた。40歳になる一人息子の世話をするために、はるばる中国から渡豪してきたという。世話焼きタイプのアンティは私に対しても、シャワーを浴びたのか、もうご飯を食べたのか、と聞いてくれた。英語が話せないので構わず中国語で勢いよく話かけてくるが、いつも身振り手振りも交えて私に伝えようとしてくれていた。また時には夕飯をおすそわけしてくれたりと、愛すべき中国のおばちゃんなのだ。台湾のシェアメイト達も温かく迎えてくれて、ここでも親日家で感じの良い台湾の子達に恵まれたことを嬉しく思う。
住人の数が多い分、食糧のストックも個々が所有する棚一面に揃えられており、食べ物が多い環境は、やはりゴキブリとは切っても切れない縁だ。朝一番の電子レンジの中にはきまって先客(ゴキブリ)がいる。また、蟻達はというと、パンやお菓子の袋の少しの隙間を狙って侵入してくるが、ギョッとするのは最初だけで、しばらくするとあまり気にならなくなった。
ただ一つ、日ごとに気になってしょうがなかったは、アンティのイビキだった。その部屋の空気を圧する、地鳴りのようなイビキは、意識すればするほど眠れなくなり、日に日に悩みの種となっていった。寝不足で迎えた朝は気分が悪く、稼働率30パーセントぐらいで生活していたので、安眠を第一に次第にオウンルーム(一人部屋)を切望するようになる。
その点、家の中は常に清潔に保たれており、ゴキブリの姿も滅多に見かけなかったし、わりともの静かな女性だったので、睡眠確保という当初の私の目的は達成された。それに、同じイラン人でも家に遊びに行った時に、お酒や手料理を次から次へとふるまってくれて、歓待ムードに包まれたこともあった。
オーストラリアに来て毎度ながら思うことだったが、人間関係を国の文化という大雑把な括りだけでは読み解くことはできない。私は、つい早合点して次々に仮説を組み立て、変な気遣いまでしてしまい、そしてそれらは虚しく上滑りしていた。上手くいかない時は、それまでだ。
早速電話をして、インスペクション(下見)のアポを取った。電話での雰囲気から、陽気で大らかな印象を受ける。地図で確認しながら目的地に向かって道路を歩いていると、オーナーのおじさんと思われる人がわざわざ外に出て待ってくれており、明るく迎えてくれ、家の中を案内してくれた。
このフラットはメゾネットで1階がキッチン・リビング・ダイニング。2階に2部屋とバス・トイレがある。窓がたくさんあって、風通しが良い。丁寧に整頓されて綺麗で、それに温かくて開放的な雰囲気で溢れていた。
そして交渉に入るのだが、ホテルの仕事がもうじき6ヶ月の満期を迎え、その後ダーウィンを出ることも考えていたので、1ヶ月半程の滞在になるかもしれないことを伝えると、ミニマムステイ(最低滞在期間)の制約は無いから心配しなくていいと言ってくれた。そして一番心配していた、今別のシェアハウスに住んでいるので、入居を2週間待ってほしいという私のあつかましい願いも「あぁ、OKだよ」と嫌な顔一つせずに快諾してくれたのだ。さらにはDeposite は取らない主義だから、2週間後にここに入居した時にその週の分のレントを払ってくれればいいよ、と何から何まで寛大だった。
話の流れで、今住んでいる別のシェアハウスがちょっと居心地が悪くなって主な理由は節約のための制約が多くてという状況をかいつまんで説明すると「そいつはsillyだな」と言っていた。
帰る時に「やっぱり私何かちょっとでもお金を置いていった方がいいと思うんですけど・・・」と言うと「君の言葉を信じるよ」と言ってくれ、笑顔で手を振って別れた。
太陽みたいな人が優しさを与えてくれて、私の目の前は一気に開けていくことに。家に帰る足取りの軽いのなんの。
そしてその日の晩、おじさんからメールが。
「君の今の状況を考えると、ハッピーじゃないよね。もし君が今すぐここに移りたいなら、すぐに引っ越してきてOKだよ。レントは2週間後からでいいから」と驚くようなメールをくれたのだ。
さらには、「I could see last night an unhappy person in you! I look forward to seeing a happier Maiko.」という素敵なメールを送ってくれた。
単純な私はもう既にHappier Maikoになっていた。翌日仕事が終わると、一目散に帰宅し、目にもとまらぬスピードで引っ越しの荷造りをし、イラン人のシェアメイトに別れを告げて、3度目の引っ越しを終えたのだった。
11月も終わりを迎える頃には、Toadsと呼ばれる毒性ヒキガエルが大繁殖する。そろそろ雨季が始まるサインだ。彼らは雨上がりの夜、芝生の上を飛び跳ねていたり、稀にトイレの便器の中にも潜んでいることもあるので要注意だ。
気温はさほど変わらないが、湿度が著しく上昇するむさ苦しい季節で、町ゆく人々が不機嫌になっていく。また、マンゴーが旬の季節でもあるこの時期は、別名Mango Madnessとも呼ばれ、窃盗事件が最も増加するのだという。
暑さで判断力が鈍るのだろうか。日本でいう、ぽかぽか陽気の春先に変質者が増えるといった具合か。しかし、年の瀬が近づく11月。年越しできないという不安が募っての行動なのかと思うと、切迫したものを感じる。
そして12月になり本格的な雨季を迎えると、市内にいたバックパッカー達はこぞって他の町へと移動していったようである。ダーウィンの町はゴーストタウンと化し、静かなクリスマスが訪れる気配を感じていた。これはこれで良いものだ。
そして迎えたクリスマスの朝の出来事。
シェアメイトのおじさんが「サンタクロースから君にプレゼントが届いてるよ」と言い、クリスマスのラッピングがされた小さな箱とカードを渡してくれた。
なんだろう、チョコレートかな?と思い、包装をほどき箱を開けると、それは本物の真珠のネックレスだった。
「こんなに素敵なプレゼント・・・本当にありがとう!!私には良すぎるよ」
すると、 おじさんは「かつてはたくさんの日本人が、真珠の採取でダーウィンを訪れていたんだ。だからこれはクリスマスプレゼントであり、ダーウィンから日本へ持ち帰るプレゼントだよ」と言ってくれた。
サンタクロースからプレゼントをもらうなんて10歳の時以来で、童心に返ったような気分なる。それにおじさんの粋な心遣いと優しさが、本当に嬉しかった。
その日の夜は、おじさんとおじさんの友達2人と一緒に、フラットの敷地内にあるプールでビールを飲んでいた。
友達の一人は、元ボクサーで半年前に試合で片耳の聴覚を失った、美容師のオーナー。底抜けに明るい。
もう一人は向かいのフラットに住む兄ちゃんで、籍を入れていない元彼女との間に8歳になる子供がいる。子供は数メートル離れた近所のアパートに元彼女と一緒に住んでいて、この日も子供が兄ちゃんの所に遊びに来ていて、楽しそうにプールで一緒に泳いでいた。しばらくすると元彼女が子供を迎えにきて、帰っていった。こうゆう家族のカタチもあるのだ。
シェアメイトのおじさんは3児の父で10年前に奥さんと離婚している。第一子はおじさんが17歳の時に生まれたそうだ。
バックグラウンドが全く違う私たちが、一緒にプールにつかってビールを飲んでいることが、なんだか奇跡だよなーと思いながら。他愛無い話をして、笑いながら過ごしたクリスマスの夜だった。気がつけば4時間近くプールに入っていたので、帰る頃には皆手のひらの皮がシワシワだった。
◆アリススプリングス 数十年に一度、川が流れる町
ダーウィン最後の日は、シェアメイトのおじさんと近所の人に手作りの巻き寿司をふるまい一緒に食べた。そして、シェアメイトのおじさんどうかずっとお元気で、、という願いを込めて折り紙でくす玉を作ってプレゼントした。おじさんはすごく喜んでくれて、別れを告げるのは寂しかったが、きっとまたどこかで会えるようなそんな気がしていた。
さてここから、The Ghanというダーウィンとアデレード間を結ぶ、長距離列車の旅が始まる。最初の目的地は、アリススプリングスだ。約20時間という乗車時間の中で、ゆったりと列車の旅を楽しんだ。窓の外は、鬱蒼とした熱帯雨林から次第に赤土へと変わり、アウトバックの乾燥地帯へと足を踏み入れる。季節をも縦断しているような景色を、ボーっと眺めながら物思いに耽る。
アリススプリングスの駅に到着すると、まんべんなく晴れ渡った青空と、新しい土地から運び込まれる乾燥した空気で、とてつもなく新鮮でワクワクした気持ちになった。この特別な空気は、ここがオーストラリアで一番好きな場所になるのではという気配を感じさせていた。
そしてアリススプリングスと表示された駅の看板には、THE HEAT, THE SOUL ,THE CENTREと書かれていた。
約一週間前、ここアリススプリングスでは大規模な洪水があちこちで起きていたという。今回の洪水により、普段は干上がっているTOD’S RIVERに水が流れていた。これは約20年ぶりの出来事だそうで、ドリームタイムという古くからのアボリジニーのお話では、この川が水に満たされる時、女性にとってとても大きなヒーリング効果があるのだと聞く。川の水は母乳の象徴なのだそうだ。幻のTOD’S RIVERが流れる、砂漠の真ん中にあるその町は、どこへでもいけそうな解放感があった。
何か他の場所にはない、大きな力の計らいを感じた。そして人間の生命力に感動した場所だ。そのような人々が集まっていた気がする。それぞれの時間の流れを身にまとっているような。人が居るってこんなに居心地が良いものなんだと、バッパーで感じたのは初めてだったかもしれない。
毎日気持ちよさそうに日向ぼっこをしている、白い靴下を履いたみたいな模様の猫。
ダーウィンから、アデレードを目指して自転車で旅をしている日本人。
ウルルでツアーガイドとして働く日本人。
一人でサバイバルキャンプをしていた、ミャンマー人の女の子。
シベリア鉄道でロシア・中国を旅して、オーストラリア全土を渡り歩いているフランス人カップル。
イタリア人の二人組のおじさん。一人は物書きで、旅のエッセイをイタリアで出版したそうだ。
数年前に病気で両目の視力を失ってしまった全盲のドイツ人のおじさんは、一人でオーストラリアを旅しているのだと言う。
私達は数日、数時間、時には数分を共有するだけの旅人だ。
しかし、互いに語り合うことで、旅の目的は果てしなく広がっていく。かりそめの縁であっても、大変意味深いものとなっていくのだ。
◆Urulu
旅行のパンフレットや世界の旅番組等で見慣れすぎているせいか、実物を目にした時も、これが噂のUruluか、とさほど大きな感動は生まれなかったが、巨大岩を目の前にした時心の中がシンとなるのは、やはりなにか大きな力の存在を感じた。そういったスピリチャルなものをビシビシ感じられる体質ではないが、この場所を神聖なものとして守り抜いてきた人々の、気のエネルギーみたいなものもあるのだろうか。
それに、光による七変化はやはり一見の価値があるものだった。
日が落ち始め、巨大岩は真紅に燃える。夕焼けに染まる背景に、ふもとをライトを灯した車が小さく走っていく。そして世界が黄金色に変わる瞬間は、まさに圧巻だった。しばらくすると静かな漆黒に包まれる風景への変化は、一本の映画を観ているようだった。
翌日、Uruluの周りにあるトレッキングコースを歩いていると、蟻の行列のようにして、ほぼ直滑降に近いUruluの断面をよじ登っている人達の姿が見えた。これも噂に聞いていた通りだが、聖地だと言われている場所を、炎天下の下わざわざ登ぼる、この意識が全く分からない。
参加したツアー内で、話の話題がUruluに登ることの如何を問うトピックになった時、神聖な場所であるUruluを尊重して、むやみに登るべきではないという考えで一致した。そしてその中で一人のイタリア人女性の「私達は教会に登ったりはしないわよね」という言葉は妙に納得した。日本でいうと確かに私達は神社や寺に登らないし、実際にそんな者がいたのならばとんだ不届きものと糾弾されるだろう。
◆アリススプリングスのアボリジニーについて
アボリジニーには古くから受け継がれている、刑罰があるという話を、ガイドから聞いた。中でも衝撃を受けたものは、何かの実だか葉だったかは忘れたが、自然の植物から摘出したエキスは、数日間盲目になってしまうくらいの劇薬で、それを目にこすりつけられ、山の中に放置される。そしてそこから自力で戻って来たものだけが、またコミュニティー内での生活が許されるというものだ。
その他には、Spear to the leg という、その名の通り足に矢を貫通させるという、想像するだけで顔が歪む仕打ちだ。急所を外して、神経が通っていない所を狙うらしいが、後遺症が残ることもあるそうだ。
そういえばダーウィンにいる時、足の不自由なアボリジニーの人たちをいたるところで見かけた。もしかしたら、彼らも過去にSpear to the letという刑罰を受けた者たちなのか?
ガイドに尋ねたところ、「It’s our fault」と言う。
白人たちが、アボリジニーの人々が遺伝的に分解できないアルコールや砂糖を与えたことで、糖尿病や障害を持って生まれる人がいるのだという。分解できない体質と知って、アルコールや砂糖を与えたの?という質問には、「そうだ」と短く答えそれに続く言葉は無かった。
ダーウィンの所々で見かけた、昼夜構わず泥酔し、道端で物乞いをするアボリジニー達。彼らは自らの体がアルコールを分解できない体質と知りつつも、アルコール依存から抜けられないのか。そのジレンマを思うと、やるせない気持ちになる。
一方、アリスにいるアボリジニーの人達はというと、穏やかに感じた。道端で今何時?と聞かれたり、すれ違い際に手を振って挨拶をしてくれたりもした。路上で泥酔しているアボリジニーも見かけなかった。これも聞くところによると、アリスではアルコールの購入がかなり厳しく制限されていて、アルコールショップの前には必ず警官が立っており、購入量をチェックしているのだという。
◆アデレードからKangaroo Islandへ
再びThe Ghanの列車に乗り、アリススプリングスからアデレードを目指す。今度は単色同一だった赤土の景色から、次第に色が加わり、草原地帯へと変わる。南北を縦断するアウトバックの風景は、25時間の列車の旅の中でも、全く飽きのこないものだった。
アデレードは、碁盤の目のように区画整理された綺麗な街並みだ。シティの中心を南北に通るキング・ウィリアムストリートがメインロードである。国王の名のついた道路を横切る道路があってはならないとの理由で、交差する道路は左右で違う名前となっているという。このことが、後にレンタカーを借りる際に方向音痴の私のコンパスを余計に狂わすことになる。
アデレードでしばらくの間滞在していたのは、市内でも最小のバッパーで、実にこじんまりとしていた。受付やその他雑用等を3人のおっちゃん達が変わりばんこで担当しており、朝になると慣れた手つきでパンケーキを焼いてくれる。毎朝パンケーキの良いにおいで目覚めるという、幸せな朝を体験できる宿だ。
2月から3月にかけて、アデレードではFringe Festivalという年に一度の芸術祭があるため、町はにぎわいを見せており、バッパーも毎日満員だった。次第に静かな自然の環境に身を置きたいと思うようになり、カンガルー島へ行こうと決めた。
東西に150km、南北へと50kmに伸びるその島は、東京都の約2倍の面積だ。そうと聞くと、これなら私でも自転車で一周できるのではという気になり、短絡的な思考で島一周を企てる。
これに対して、バッパーの3人のおっちゃん達は一様に反対した。小さく感じるその島だが、道のアップダウンが激しく、おまけに冷たい強風にあおられる為、サイクリングには不向きな気候なのだと言う。ツアーに参加するか、車を持っている人で且つカンガルー島にいきたい者が現れるまで待ったほうがよいということだ。しかしこのアデレードの町中にあるバッパーは、仕事を探している若者達で溢れ返っており、離れ小島を観光したいといううかれた様子の者が見当たらなかった。
あてのないものを待ち続けるのというのは、どうも性に合わないし、なにより実際にカンガルー島がどんな場所なのか自分の目で見なくては納得がいかない。
思い立ったら吉日で、Gumtreeで中古のマウンテンバイクを購入した。オンボロの安モノは買わない、信頼できそうなオーナーから買うという条件のもと見つけたのは、$150のマウンテンバイクだ。オーナーも良さそうな人である。
実際にその自転車に乗ってみると足がつま先しか地面につかず、そこに私の運動音痴がプラスされると、頼りないバランスだったが、それもしばらく乗っていると慣れというもので、さほど気にならなくなった。カンガルー島を自転車で一周したいと思ってるんだ、と話すと、それは楽しそうだねといって親切なオーナーは、旅の足しになればと、その自転車を$110にまけてくれた上、ヘルメットと携帯用の空気入れをつけてくれたのだった。
2日後、必要最低限の荷物だけ担いで、自転車とともにフェリーに乗り込んだ。目指すはもちろんカンガルー島だ。
その日は波が荒く、船に乗っていた40分のうち30分間トイレに立てこもり続けた。トイレの中で島に到着したというアナウンスを聞き、船酔いを引きずったまま船から降りた瞬間に、早くも自転車と共に島に上陸した意味を、自らに問いたくなる景色が広がっていた。そこから続くどの道も、突然の急勾配なのだ。幸いYHAが歩いて5分もかからないところにあり、到着してすぐに泥人形のようにベッドに倒れ込む。その日は久しぶりに深く眠った。
そして、翌日からサイクリングを開始。
なるほどバッパーのおっちゃん達は正しかった。島の80パーセント以上が丘陵地帯なのではと感じるほど、急勾配の連続である。全力で坂を上がりきった次の瞬間には、坂を全速力で下がっていく。この滑稽な運動性の中で、はて私は一体何をしているんだろう…?と考えると面白くなってきた。考えれば考える程おかしい。そんなことはおかまいなしに、美しい自然は背景を支えているし、すれ違いざまに車のドライバー達が声援を送ってくれたりする。
そういえば、空の澄み具合や、空気の香りはタスマニアに似ていた。自然の色彩が鮮やかなところも。
片道1〜2時間程の距離は自転車で走り回った。このような、限定された範囲内でも好きなように自由に飛び回るというのは、子供の頃の夏休みのような、何か懐かしい思いがした。小学生が隣町まで自転車で出かけるような冒険感覚を充分に味わえた気がする。
ただ、かねてから行きたいと思っていた場所は主に島のはずれに点在しており、この島の急勾配を目の当たりにした今となっては、自転車でそこまで辿り着くのは気が遠くなる話だった。そこで、たいした根気の無い私は、あっさりとレンタカーを借りることになる。
しかし、それには問題があった。島を自転車で一周する!と勇んでアデレードを出た私は、まさかレンタカーを借りることになるとは想像もしておらず、国際免許証をアデレードのバッパーに置いてきてしまった。レンタカー会社にその旨を伝えると、やはり車をレンタルする際に国際免許証の提示が必要だと言われた。そこで少しねばって、国際免許証の顔写真が載ったページを写真で取って、メールで送るというのはどうかと聞いたところ、しばらく電話越しで担当者が確認をした後、それであれば特別に許可しようということで了解を得ることができた。そして、すぐさまバッパーに電話をして、事情を説明する。バッパーに置いてある荷物の中から国際免許証を探していただき、どうかその写真をメールで送ってほしいのです、と申し出た。私のこの図々しいお願いにも関わらず、バッパーのおっちゃんは「わかった」と言い引き受けてくれた。
おっちゃんのお蔭で晴れてレンタカーを借りることができ、オーストラリア国内で2番目に大規模な野生のアシカの自然保護区であるSeal Bayを経由して、島の西南にあるFinders Chase国立公園に向かった。
そこにはRemarkable Rocksと呼ばれる岩がある。波の浸食により自然の経過でできたと言われているその岩は、直訳の名の通り、注目するに値する岩だった。切り絵みたいにくり抜かれた岩から青空を眺めると、マグリットの絵画を見ているようだった。無秩序で美しいまるでオブジェのように佇む岩は、サルバトール・ダリのような世界観だ。
同公園内にあるSnake Lagoon Hikeでは岩肌を辿ること約45分、そのトレッキングのゴールは入り江だった。出発地点からも、課程の道のりからも想像もつかないラストの光景が広がっていた。トレッキングの奥義のようなものを感じる。
ここで、両側に大きい荷物を吊り下げた自転車を脇に、休憩している初老の男性を見かける。この人はもしや…と思い話しかけてみる。
彼はエリックというオランダ人で、テントの四隅はネズミにかじられたりしつつも、風雨をしのいでキャンプをし、やはりシティバイクで島を一周しているという。この話を聞いて、私はただただ感服する思いだった。
エリックに教えてもらった、フリーキャンプ場があるというParndanaという場所が次なる目的地となった。
そして着いた場所は、キャンプ場といっても、パブの使われていない駐車場で、シャワーや電源はもちろんのこと、トイレも見当たらなかった。パブで聞いてみると、シャワーはパブに内にあり、$3で使用可能、トイレは道の反対側に公衆便所があるという。
夜になるまでまだ時間があったため、町にあるパン屋の店員に教えてもらったおすすめのビーチへと車を走らせた。メインロードを北上していくと突き当たる、Stokes Bayという場所で、岩のトンネルをくぐり抜けると、白い砂浜のシークレットビーチが広がっていた。
このように、カンガルー島の自然には、冒険心をくすぐるようなしかけがあちこちにある。自然のしかけを楽しむというのは、とても純粋な気持ちになるものだ。
◆Flinders Ranges
カンガルー島での小さな冒険を終え、アデレードへ戻った時には、次の目的地が決まっていた。
Flinders Rangesという、アデレードから450km北に位置する山脈で、その一体が国立公園になっている。今回はアデレード市内のレンタカー屋で車を借りる。
出発日の前日、バッパーのおっちゃん達に「キャンプ用品は持っているのか?」と聞かれ「寝袋とKマートで買った安いテントしか持っていない」と告げると、やれやれといった表情で、「キャンプセットを用意してやるよ」と言い本当にキャンプ用品一式を準備して貸してくれたのだ。
その内訳は、ガスコンロ、ガスボンベ、鍋、フライパン、食器類、まな板、包丁、フライ返し、おたま、クーラーボックス(親切に氷まで入れてくれてあった)、ライト、ふきん、スポンジ、洗剤だ。
これは本当にありがたかった。逆にこれらのアイテムを持たずに、私は一体どうやって人里離れた場所で生き延びようとしていたのか。ここでまた自分の考えの甘さを反省するべきだ。バッパーのおっちゃん達には、きっと何から何まで世話のやけるヤツだと思われていたことだろう。
Flinders Rangesへ出発当日。市内のレンタカー屋で車をピックしたのはよいのだが、徒歩だと15分で着く距離にあるバッパーまで運転するのに迷い迷った挙句、1時間半かかりようやく辿り着く。自分の方向音痴の実力を恐ろしく感じ始め、この先どうなるかと思うと心細いかぎりだった。
決死の思いでアデレードを出発。30分ほど車を走らせると、やがて信号が無い道路へとつながり、更に1時間もすると車の数も減り次第に喧騒感が薄れていった。道の両側から広がるはるか先に、山脈が現れると、新しい土地に突入したという清々しい気持ちになった。遥かかなたを目指すドライブというのは、本当に気持ちが良いもので、その両サイドを流れる景色にもいちいち溜息が漏れる。
Flinders Rangesで特に興味深いのは、約4億5千年前の地殻変動により生まれたと言われている、Wilpina Poundという巨大なクレーターだ。その周辺の道は険しく、トレッキングでしか辿り着くことはできない。しかし、あろうことか、この日は記録的な猛暑日であり、熱射病や山火事の危険性が高くなるなど安全面の理由ですべてのトレッキングロードが閉鎖されていた。
残された道は、車でその周辺のオフロードを駆け巡ることだ。景観が美しいScenic Driveをあちこち走り回ることにした。ちなみにすれ違う車は、1日に4〜5台程で、灼熱の山脈地帯でアウトバックを感じられた。
車から外に出ようものなら、熱風に煽られ、ジリジリと肌を焦がす太陽の下では5分立っているのもやっとな程、体力が消耗していく。人間にはどうにもコントロールできない自然を感じる。また、人間も自然の一部であるということも。そのことを改めて感じたことは、トイレだった。
びろうな話で恐縮だけれど、キャンプ場以外の場所ではトイレが見当たらなかったため、その辺の草むらで用をたす回数が増えていった。それに慣れてしまうと、それで充分だと思えてくる。なぜ人間はわざわざトイレを立派にこしらえ始めたのだろうか。音楽が流れるようにしてみたり、ウォシュレットを付けたりと、そこに快適さを求めるのだろうか。
外気温45℃という暑さのせいか、野生化した本能なのかは分からぬが、そうゆうことを真剣に考えだした。そして大自然を前にすると、何が正しいとか間違いなんていうのはいかに愚問であるかということを感じるのだった。
自然以外の何にもない場所に身をうずめるようにして立っていると、本当に自由を感じられる。そこには孤独や不安や焦りといった概念はない。
そういった類の悲壮感から解放された瞬間だった。どこにでも道があることを知った。そしてどこへでも進んでいけるということも。
夕暮れ時が近づくと、西の丘を目指してそこから夕焼けを見た。
赤い土埃をレンタカーの車体に浴びながら、舗装されていない道路を駆け巡った2日間だった。アデレードのバッパーに帰り車を見てみると、車体に少し傷がついていることに気付く。塗装が少しえぐられており、はがれかけの絆創膏のようにぶら下がっていた。
◆Road Tripの始まり
旅もそろそろ終盤に近づき、オーストラリアも残すところ1ヶ月弱となった。車の運転も少しずつ慣れてきたこともあり、このままメルボルンまでレンタカーでドライブしよう。そしてそこから飛行機でシドニーまで飛ぼう、というプランが出来上がった。
アデレードのバッパーのおっちゃん達には、散々お世話になり感謝しつくせなかった。せめてもの気持ちで、今後またこのバッパーにカンガルー島を自転車で一周したいという者が現れた時のために、自転車を寄付することにした。もしかしたら、今でもその自転車はバッパーの建物の裏の倉庫に眠ったままかもしれないが。
RoadTripが始まり、まず最初に立ち寄ったのは、Hahndorf。オーストラリアでドイツ人が最初に居住した場所だ。メインストリートにはアンティークショップやキャンドルの店、カフェレストランが並び、ドイツの小さな田舎町という雰囲気が漂う。
その後迷いながらようやく辿り着いたRobeは手作りアイスクリームで有名な可愛らしい町。またヴィクトリア州有数の釣りスポットでもある。海岸沿いを散歩していた時のこと。大きめのウニが落ちていると思って近づいてみると、ハリモグラだった。
更に南へ向かって車を走らせること数時間、Mt Gambierに到着する。
この町は、アデレードからメルボルンのちょうど中間地点に位置している。そしてなによりの見所はブルーレイクという、その名の通り青い湖だ。それは、そのシンプルな名前から想像する以上の青で、目の覚めるような、空よりも青いコバルトブルー色の湖だった。この青さに関しては、いくつかの説があるようで、湖の中に蓄積された石灰石の中に青色を強く反射する物質が含まれており、空の青さを反射しているからというものや、蛍光性を帯びた有機物が、季節によって水面に溶け出しているからといった説明が書かれていた。
この湖が神秘的なのは、季節で色が変化する点だ。青い湖は他の土地にもあるのだが、一年を通してこんなにも劇的に色が変化する湖は、世界でも珍しいそう。ちなみに11月から2月頃がもっとも鮮やかなブルーが見られるという。それ以外の月は、グレーがかった緑色やはがね色だそうだ。
このさわやかな湖に反して、この土地で行き当たりばったりで辿り着いた宿は、元刑務所というバッパーだった。重々しい門をくぐると、中には更に塀に囲まれた建物がいくつかあり、その中に小さな教会や宿泊棟、談話室、キッチンが迷路のように入り組んでいる。随所で受刑者の生活についての説明や、服役中に自殺した受刑者の名前まで記されていた。
私の泊まった部屋は、窓があり、他のバッパーよりむしろ明るくて綺麗だったが、Cellと呼ばれる監房タイプの窓なしの部屋もあり、より監獄気分を味わうことができるようだ。
監獄宿から車で10分の距離に、Umpherston Sink holeという公園があった。ここは石灰岩の大地が浸食されて巨大な穴があいており、その空間に草木が生い茂り、花が咲き、地中庭園になっているのだ。この場所で、私は文字通り空を見上げた。こんなジブリの世界みたいなものが、突如出現するのだから驚きだ。
ここから内陸を北上して向かったCoonawarraという場所はワインの生産地だ。
オーストラリアで最も有名なワインの産地バロッサ・バレーが50軒のワイナリーを構えているのに対し、Coonawarraは30軒とこじんまりとしているが、通好みの赤ワインの名産地で特にカヴェルネ・ソービニオンが有名だ。Penolaという町からワイナリー街は始まっており、Coonawarraへ南北にのびる道路沿いにずらりとワイナリーが並んでいた。
運転していても色々なワインを試飲したい者は、試飲の際に口の中でワインを味わった後、飲み込まずに吐き出すのだと聞き、各ワイナリーには専用の吐き壺なるものが用意されていた。しかしこの吐き壺を利用するのはなんとなくためらわれ、試飲したワインはすべて飲み干してほろ酔い状態で白ワインを自分用に、カヴェルネ・ソービニオンをこれから訪れる先へのおみやげとして購入した。
Port MacDonell, Portland, Port FairyとPortのつく港町を巡り、海沿いのドライブをする。
その中で、Port Fairyはおとぎ話めいた名前の響きが気に入って、この町をゆっくり訪れてみることにした。ヴィクトリア州で一番古い町だそうだ。泊まったYHAは小さいながらも立派な中庭があり、それを取り囲むようにして宿泊部屋とキッチンがあった。ヨーロッパの田舎にある小さな宿みたいだ。この日の宿泊客は少なく、静かな町という印象だったが、毎年秋にはフォークフェスティバルが開かれ、町中の宿泊施設がどこも満員になる程の盛り上がりをみせるそうだ。
広場ではマーケットが開かれており、地元でとれた新鮮な野菜やフルーツ、ジャムなどが売られていた。この町で、忘れられないものとなったのは、マーケットで買ったイチゴの甘さと、道端でアイスクリームを食べていたおじいちゃんの幸せそうな表情だ。
更に海岸沿いを車で走らせ、いよいよグレートオーシャンロード本番の舞台に近づいてくる。
PortCambellは、よく絵葉書になっているTwelve Apostlesから一番近い町であり、その日も観光客で賑わっていた。特に旧正月でホリデーを満喫している、中国人の団体客がひときわ多かった。宿もあちこちでNO VACANCYの看板を掲げており、バッパーも割高料金であったが、残りわずかの空き数のところをギリギリ予約が間に合い、その日の宿をなんとか確保することができた。
今までオーストラリアを旅してきた中で、男女混合のMix Dormで、女性は私ただ一人という状況は何度かあった。しかし、男だらけのオージーライダー達の部屋に、なぜか迷い込んだかのごとく日本人の女私一人という状況はここが初めてで、笑えた。このオージーライダー達は全員メルボルンからバイクを走らせ、グレートオーシャンロードをツーリングするのだという。彼らはとても気さくで、部屋の温度やいびきの心配など色々と気を遣ってくれた。
夜は一緒に飲もうぜと誘ってくれ、私はCoonawarraで買った白ワインを冷蔵庫に入れて冷やしておいたのだが、数10分後にキッチンに戻った時には何者かによってそのワインは飲み干されており、空瓶だけが虚しく放り出されていた。
それを見たスキンヘッドで強面のオージーライダーが、周りにいた人に聞いてくれたのだが、もちろん正直に白状する者はいない。
すると別のオージーライダーが「まぁこれでも飲んで元気だせ」と言って、缶のJimbeanを分けてくれたのだった。初めて飲んだJimbeanは思っていた以上においしかった。
そして陶芸家のオーナーと再会。奥さんも温かく迎えてくれ、感涙が込み上げてきた。更にありがたいことに、せっかく来てくれたのだからゲスト用の宿泊施設に泊まっていきなさいよ、と言ってくれた。おみやげに渡した赤ワインを一緒に飲みながら、約1年ぶりに交わす会話はその都度懐かしさが込み上げてきて、胸がいっぱいだった。
今回のRoad Tripを振り返ると、走行距離は10日間で約1500kmだった。日本にいる時には、ペーパードライバーで、免許取得してから100km以上の道のりを運転したことすらなかったことを思うと、より達成感が募る。行きたい場所に行って、見たい景色を見て、やりたいことをやった。自分が自分のためだけに持った、初めての時間だったのかもしれない、などと思いながら感慨に浸っていた。
この数か月後、スピード違反による罰金約$200の請求書が海を越えて届くことになるとは露とも知らず…。
ちなみこの人生初のスピード違反を犯した場所はPrinces freewayのLittle River, Point Wilson Roadで、地図で確認したところ、GeelongからMelbourneへ行く途中にあった。後で知ったのだが、この場所はスピード違反多発地点で、毎日100人以上が検挙されているらしい。全く不覚だったとしかいいようがない。事故を起こさなかったということだけで良かったと思おう。
幸い無傷でレンタカーを返却し、メルボルンから飛行機で向かった3度目のシドニーでは、元シェアメイト、アナンタとの再会。アナンタは相変わらず太陽とひまわりが似合うような男だった。2年前まだオーストラリアに着いて間もなかったシドニー時代に、幾度となく励まされたかを思い出す。
その後Brisbaneを経由してNoosaで数日間過ごした。海で泳いでビーチに寝転んだり、SUP(スタンドアップペダルボーディング)をしたり。SUPで水面を移動していくと、目の前がスーッと開けて海へとつながっていく。更に遠くの方では山々が見えたりと、風景画を切り開いていく感覚だ。今回のオーストラリアで最後の土地は、ボーっとした場所が良いと思っていたので、Noosaはそれにぴったりの環境だった。
そしてついに迎えた日本帰国の日。センチメンタリズムは如何ほどになるかと興味深いところであったが、期待していたほどのものはなかった。日本帰国が待ち遠しい興奮も、オーストラリアを去るにあたり込み上げてくる感慨もなく、その時の心境がどこにも属していないことを知った。
独り旅に徹した際に味わうこの浮遊感は、私の求めていた旅の理想形であったのかもしれない。
◆おわりに
巷で使い古されてきた言葉“自分探し”。私もこれと題して、脱OL、渡豪して約2年間のワーホリを終え日本に帰国した。そして感じた。
2周まわって自己視察の後に辿り着いたのは、結局なんてことはない自分だったということを。オーストラリアでの経験を通して、その状況に応じて感情と戯れていた。それを傍観している自分が常にいたという気づきは、当たり前すぎるけれど、私にとっては大きな発見であった。つまり、経験に伴いどこからともなく感情というものがふっと現れて姿を消すまで、それを常に見つめている観察者としての自分は、今も昔も変わらずここにいるという事実だ。
私にとっての“自分探し”とは、常にそこにあるものを求めていたということに、振り出しに戻って気づいた。
オーストラリアに来たからには、何かを掴み取らなければいけない、何事かを成し遂げなければ、と変に力が入っていた時は意欲と称したエゴだけが空回りしていたし、奇をてらった行動をとることが個性であり自己実現と勘違いしていたこともあり、それらは単なる自己顕示で自分の本質からは遠ざかっていた。
それから1つ1つ手放して自由になっていく。
自己主張から個を見出さなくてもいい。なぜなら、自分とは常にそこにあるものなのだから。
異国の地を旅した感動は、やはりいつしか色褪せるだろうし、反省も喉元すぎれば熱さ忘れるであろうけれども、この自分がいたことに気づいた時の感覚は、この先もきっと忘れないだろう。
それに今回は一人旅の効用が大きかったように思う。自分と対峙することで、新しい可能性に気付き、目の前が開けて生きている手応えを掴んだことから始まり、旅を進めるにつれて無駄なものを削ぎ落としていく、身辺整理に近い、静かな終焉を感じた。その穏やかな静けさの中でふと考えた時に、人を大切に思うこと、人から大切にされていると感じること、果たしてこれ以上に望むものはあるのだろうか?これは当たり前のことを辿っていった先にあった、これ以上細分化できない、私のもとにおさまった普遍的事実だ。
まだあと少し旅を続けるつもりでいるが、それはボーナストラックのような、おまけの旅だと思っている。新しい旅の中でも、普遍的なことを考え続けていきたい。