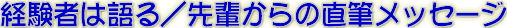オーストラリア移住論
→MORE
第一の関門:VISA
関連&参考
ビザの原理原則/技術独立移住永住権/頻繁に変わるビザ規定/専門業者さん/その他の永住権/永住権以外の労働できるビザ
第二の関門:生計
ビザ用のスキルと生計用のスキル/「日本人」というスキル/世界のオキテ/オーストラリア仕事探しサイト内リンク
戦略と戦術(その1)
フォーマット設定/欲望のディレクトリ~永住権だけが全てではない、手段と目的を明瞭に意識すべし
戦略と戦術(その2) よくある基本パターンと組み合わせ
永住権優先でいくか、ステップアップ方式でいくか/「はじめの一歩」をどうするか/利益衡量/ストレート永住権の場合の具体的戦略/ステップアップ方式の場合の具体的戦略~意外と使えるワーホリビザ/ダメだった場合~あなたにとっての「成功」とは何か?/先のことは分からない/
今週の一枚ESSAYより
「”海外”という選択シリーズ」 過去回INDEX
ESSAY 452/(1) ~これまで日本に暮していたベタな日本人がいきなり海外移住なんかしちゃっていいの?
ESSAY 453/(2) ~日本離脱の理由、海外永住の理由
ESSAY 454/(3) ~「日本人」をやめて、「あなた」に戻れ
ESSAY 455/(4) ~参考文献/勇み足の早トチリ
ESSAY 456/(5) ~「自然が豊か」ということの本当の意味
ESSAY 457 / (6)~赤の他人のあたたかさ
ESSAY 458/(7) ~ナチュラルな「まっとー」さ~他者への厚情と冒険心
ESSAY 459/(8) ~淘汰圧としてのシステム
ESSAY 460/(9) ~オーストラリアの方が「世界」を近く感じるのはなぜか(1)
ESSAY 461/(10) ~オーストラリアの方が「世界」を近く感じるのはなぜか(2)
ESSAY 462/(11) ~日本にいると世界が遮断されるように感じるのはなぜか ~ぬくぬく”COSY"なガラパゴス
ESSAY 463/(12) ~経済的理由、精神的理由、そして本能的理由
ESSAY 519/放射能→海外というトコロテン式思考について - Lesser of two evils principle
シドニーで仕事を探す方法
→MORE世界と日本の潮流
→MORE
GFCと世界経済のメガトレンド
オーストラリアにおける影響 語学学校や留学、ワーホリや生活面、永住権やビザ
対策と展望~為替レート
渡豪の時期論
国内市場の縮小と海外シフトと新たな就職機会とキャリア
オーストラリア留学/ワーホリ/移住の新しい局面
20年前の発想は変えるべき
オーストラリアにおける影響 語学学校や留学、ワーホリや生活面、永住権やビザ
対策と展望~為替レート
渡豪の時期論
国内市場の縮小と海外シフトと新たな就職機会とキャリア
オーストラリア留学/ワーホリ/移住の新しい局面
20年前の発想は変えるべき
語学学校論
予算と費用
学校の選び方
英語学習論
→MORE
オーストラリアの語学学校って「こんな感じ」 Part1、Part2
ビザの取得と活用法
1.ビザ選択の基準
2.学生ビザの取得方法(1):日本国内
3.学生ビザの取得方法(2):オーストラリア国内
4.ビザ実戦活用ガイド
滞在延長方法論~いわゆる「ビザ取り学校」について
通学期間
語学学校の効能・効果
ビザの取得と活用法
1.ビザ選択の基準
2.学生ビザの取得方法(1):日本国内
3.学生ビザの取得方法(2):オーストラリア国内
4.ビザ実戦活用ガイド
滞在延長方法論~いわゆる「ビザ取り学校」について
通学期間
語学学校の効能・効果
予算と費用
学校の選び方
カタログショッピング的学校選びの危うさ
1.ロケーション
1-2.学校と住居のコンビネーション
2.予算
3.規模と雰囲気(個性、居心地)
4.目的、コース
5.現在の自分の英語力
6.何のために学校にいくのか?「結果を出す」留学
1.ロケーション
1-2.学校と住居のコンビネーション
2.予算
3.規模と雰囲気(個性、居心地)
4.目的、コース
5.現在の自分の英語力
6.何のために学校にいくのか?「結果を出す」留学
英語学習論
渡豪前の英語準備
英語の勉強方法
英語雑記帳
英語の勉強方法
”量の砂漠”を越えろ
波長同調/英語独特のセンス
英語教育の教授法・学校・教師/スピーキング(1)
スピーキング(2) コミュニケーションと封印解除
スピーキング(3) スピーキングを支える基礎
スピーキング(4) 現場で得る二つの果実
スピーキング(5) ソリッドなサバイバル英語とグルーピング
リーディング(1) 新聞
リーディング(2) 新聞 (2)
リーディング(3) 小説
リーディング(4) 精読と濫読
リスニング(1) リスニングが難しい理由/原音に忠実に
リスニング(2) パターン化口語表現/口癖慣用表現/長文リスニングのフレーム
リスニング(3) リエゾンとスピード
リスニング(4) 聴こえない音を聴くために
ライティング 文才と英作文能力の違い/定型とサンプリング
波長同調/英語独特のセンス
英語教育の教授法・学校・教師/スピーキング(1)
スピーキング(2) コミュニケーションと封印解除
スピーキング(3) スピーキングを支える基礎
スピーキング(4) 現場で得る二つの果実
スピーキング(5) ソリッドなサバイバル英語とグルーピング
リーディング(1) 新聞
リーディング(2) 新聞 (2)
リーディング(3) 小説
リーディング(4) 精読と濫読
リスニング(1) リスニングが難しい理由/原音に忠実に
リスニング(2) パターン化口語表現/口癖慣用表現/長文リスニングのフレーム
リスニング(3) リエゾンとスピード
リスニング(4) 聴こえない音を聴くために
ライティング 文才と英作文能力の違い/定型とサンプリング
英語雑記帳
→MORE
シェア探し編
~100%英語環境でのシェア探しは成功の第一関門
留学・ワーホリ食生活向上委員会
→MORE~100%英語環境でのシェア探しは成功の第一関門
1.傾向編
1-1.概況 オーストラリアの犯罪状況
1-2.最初は活動重視、徐々に引き締めること
1-3.周囲のオージーがあなたの警備隊
2.対策編
2-1.基礎力
2-2.路上盗犯対策 「スキのない私」の演出
2-3.被害を最小限に留めるワザ
2-4.住居侵入窃盗系
3.シティとサバーブ
3-1.シティの構造
3-2.シティと他のエリアの犯罪発生率比較
3-3.シティ内部でのホットスポット(危険エリア)
3-4.歩いていけるからこそ危険
4.補足トピック編
4-1.Redfern/Eveleigh Stについて
4-2.デートレイプについて
4-3.寸借詐欺
1-1.概況 オーストラリアの犯罪状況
1-2.最初は活動重視、徐々に引き締めること
1-3.周囲のオージーがあなたの警備隊
2.対策編
2-1.基礎力
2-2.路上盗犯対策 「スキのない私」の演出
2-3.被害を最小限に留めるワザ
2-4.住居侵入窃盗系
3.シティとサバーブ
3-1.シティの構造
3-2.シティと他のエリアの犯罪発生率比較
3-3.シティ内部でのホットスポット(危険エリア)
3-4.歩いていけるからこそ危険
4.補足トピック編
4-1.Redfern/Eveleigh Stについて
4-2.デートレイプについて
4-3.寸借詐欺
留学・ワーホリ食生活向上委員会
1:料理の基本構造とその応用(1)ストック+調味料の二重構造
2:基本構造の応用 (2) 和風編
3:基本構造の応用 (3) エスニック編
4:実践&食材調達編 (1)サンドイッチ編
5:実践&食材調達編 (2)ソーセージの偉大な効用
6:実践&食材調達編 (3)お米・ごはん編
2:基本構造の応用 (2) 和風編
3:基本構造の応用 (3) エスニック編
4:実践&食材調達編 (1)サンドイッチ編
5:実践&食材調達編 (2)ソーセージの偉大な効用
6:実践&食材調達編 (3)お米・ごはん編
ワーホリ実戦講座
仕事編
ラウンド編
2年目ワーホリ論
ワーホリ・留学の実戦原理
間違いだらけの留学&ワーホリ生活 ~都市伝説の検証
→MORE
ワーホリとは何か?日本人ワーホリをとりまく環境変化
ワーキングホリデー・ビザの取得方法
二回目ワーホリ
好循環と悪循環~運命の分かれ道
「やる気低落の法則」と交換の法則
バスを制する者はシドニーを制する
「正しい地図」の入手
携帯電話の選び方、考え方
ワーキングホリデー・ビザの取得方法
二回目ワーホリ
好循環と悪循環~運命の分かれ道
「やる気低落の法則」と交換の法則
バスを制する者はシドニーを制する
「正しい地図」の入手
携帯電話の選び方、考え方
仕事編
ラウンド編
2年目ワーホリ論
ワーホリ・留学の実戦原理
間違いだらけの留学&ワーホリ生活 ~都市伝説の検証
その他一般コンテンツ
→MORE