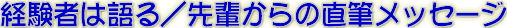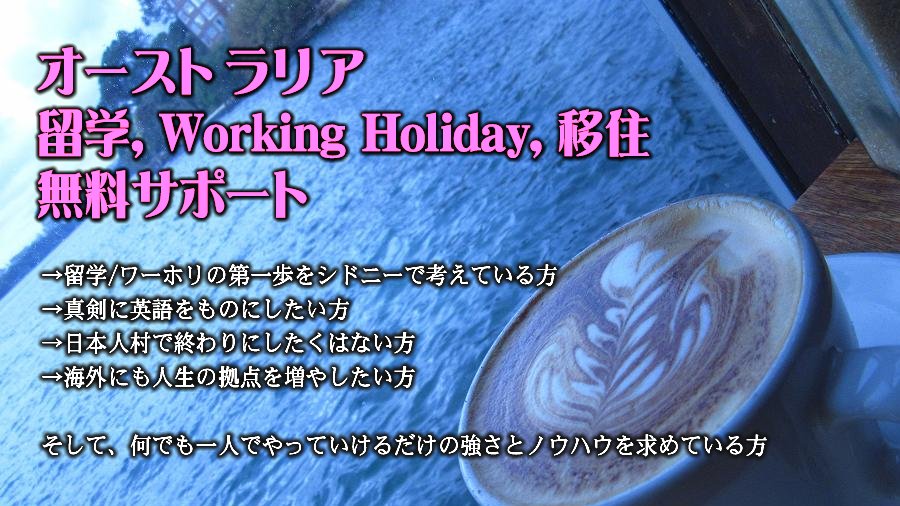−目次−
◆なぜオーストラリアに来たのか?
◆シドニー編
―すべては何となく進んでいった
―シェアハウス探し
―学校生活
−仕事について
◆ラウンドの始まり 西オーストラリアへ
−ジンベイザメと泳ぐ旅Exmouthからカリジニ国立公園
−Carnarvonでエビ釣り漁船に乗る
−初めてのファームジョブ
−チャイニーズカフェ
−シェアメイトとの思い出
◆WWOOF体験
−森の中のアートギャラリー 陶芸家のオーナーとの出会い
−窯炊き、野外映画祭、ヌードショーと日本国総領事
−量子力学とチベットのお坊さん
◆苦楽を通してみたタスマニアの景色
―タスマニア半島上陸
−New Norfolk事変
―パートナーとの別れ、Queenstownへの旅立ち
−そうだ、車を買おう
―ジョブハンティング再び
―理想の生活ってなんだろう
◆シドニー再び
―カウンセリングとパラレルワールド
◆旅の終わりに思うこと
◆なぜオーストラリアに来たのか?
◆シドニー編
―すべては何となく進んでいった
―シェアハウス探し
―学校生活
−仕事について
◆ラウンドの始まり 西オーストラリアへ
−ジンベイザメと泳ぐ旅Exmouthからカリジニ国立公園
−Carnarvonでエビ釣り漁船に乗る
−初めてのファームジョブ
−チャイニーズカフェ
−シェアメイトとの思い出
◆WWOOF体験
−森の中のアートギャラリー 陶芸家のオーナーとの出会い
−窯炊き、野外映画祭、ヌードショーと日本国総領事
−量子力学とチベットのお坊さん
◆苦楽を通してみたタスマニアの景色
―タスマニア半島上陸
−New Norfolk事変
―パートナーとの別れ、Queenstownへの旅立ち
−そうだ、車を買おう
―ジョブハンティング再び
―理想の生活ってなんだろう
◆シドニー再び
―カウンセリングとパラレルワールド
◆旅の終わりに思うこと
◆なぜオーストラリアに来たのか?
一言でいうと、何か面白そうなものを探す冒険に出たかったから。そして、自分自身を取り戻したい。
大学を卒業後、英語を使った仕事がしたいという動機で、貿易実務の仕事に就く。入社してから、気づけばもう7年目になっていた。組織に適合していくにつれて、少しずつ自分を失っていく感覚があった。そして周囲の求める人物像にシンクロしていくことに、虚しさを感じていた。
ふと立ち止まった時、「あれっ?本当の自分ってどんなんだったっけ」と思い始める。一体自分がこれからどこへ向かっていくのか、何をしたいのか、30歳を手前にして分からなくなったのだ。
それまでは自分のできること、やりたいことではなく、周囲に認められそうなこと、褒められそうなことを選択して無難に生きていたように思う。恵まれた職場環境、安定した給料、暇があれば趣味にお金を投じる。周りからは充実していていいねって言われて。そして稼いだお金は、ただなんとなく消えていく。趣味にしても、そこに情熱があったのかと言われると怪しい。自分の好奇心をつなぎとめるために、ひたすら新しい何かを探していただけに過ぎないのかもしれない。このままOLとして仕事を続けていくのか、それとも…。考えるも自分の心の声は聞こえず、目の前の課題を事務的に片づけていくだけの日々が続いていた。
そんなある日、パソコンで検索していたら、田村さんのブランキージェットシティ論に巡り合い、APLaCの存在を知る。
ブランキージェットシティとは90年代に活動していた、日本のロックバンドだ。 私が15歳の時、ブランキージェットシティの音楽に出会い思春期の自分の一部が形成された。そして、その約15年後にブランキージェットシティを通して田村さんのエッセイに辿り着き、オーストラリアへワーホリの道が開かれる。ここで人生の節目に起こる、決定的な何かを感じた。
◆シドニー編
―すべては何となく進んでいった
何となく飛行機に乗り、何となくシドニーに着き、気がつくと田村さんのお宅に到着していた。
思い返すと、当時はすべてが分かったような錯覚に陥っていたように感じる。
あぁ、そうそう、海外ってこんな感じだったよね〜という。
ちなみに、後のラウンド生活において、その錯覚がガラガラと音を立てて崩れていくことになる。
―シェアハウス探し
方向音痴の私は、とにかく道に迷った。部屋のインスペクションの約束の時間に目的地まで辿り着けず、泣く泣く諦めることになった物件もある。ある時は、オーナーである親切なインド人夫婦が、近くのカフェでコーヒーをごちそうしてくれ、インドについて話をしたり。また別の日は、アポの時間になっても現れず、連絡もつかなくなったが数十分後に「ゴメン、寝てた」と言い、現れたギリシャ人と結局1時間近く世間話をしたりもした。シドニーにいる人達の生活を少し垣間見ることができ、そこに住む人達と一瞬ではあるが関りを持つことができるので、面白い体験だった。 しかしある時は、入口付近で既に不衛生な暗いオーラ―が漂っている家があり、怖くなった私は「中は見なくて大丈夫です」とオーナーに告げ、結局そのまま帰ったということもあったが。
そんなこんなで、ほぼ10件目で決めたシェアハウスはCroydonというInner WestのSuburbエリアで、週120ドルのオウンルーム(自室にトイレ付き)、シェアメイトはオーストラリアの市民権を持つインドネシア人(体育の先生)のアナンタとUTSに通う中国人の学生ベンだ。
きっかけは、田村さんから配布された物件が載っているプリントの「ファニーなオジサン」という説明書きを見て、息抜きも兼ねて面白半分(失礼)で、見に行ってみようという軽い気持ちだった。ファニーなオッサンというからには、ちょっと小太りで50歳前後のオージーという勝手な想像をふくらませていた。
いつものように迷いながら地図を片手に歩いていると、その道の先に裸足で立って大きく手を振っているアナンタがいた。見るからに健康そうでガタイが良く、歳は30歳なので私と1つ違いだ。勝手に太ったオジサン扱いをしていたことを、申し訳なく思う。挨拶と自己紹介をした後、早速家の中を見せてもらうと、センスの良いインテリアでまとめられており、一目で雰囲気の良さを感じる。 わざわざ紅茶まで出してくれ、私達はお互いのことについて話始めた。いつの間にか話のトピックがなにやら壮大なテーマになっていることに驚いたが、やはりファニーというだけある。その語りに、やや暑苦しそうだけれど、人間味のある人生哲学のようなものを感じて、ここにしようと決めたのだ。
アナンタからは、他にも入居希望している人がいるけれど、マイコのエネルギーが良かったから君を選んだんだと言われた。ちなみに、他の入居希望者とはアグレッシブなゲイのバーテンダーとのことだった。そうして私は数日後、このファニーなシェアハウスに移動した。
アナンタは職業柄か筋肉と自分の体のプロポーションに対して、強いこだわりをもっており毎日朝一番にジムに通い、プロテインを飲んでいた。筋肉の減り具合に関しては人一倍敏感で、「最近オレの筋肉減ってない?」と時折確認を求められたりしたが、私はアナンタの筋肉を逐一チェックしている訳ではなかったので、回答には非常に困った。
陽気な性格で所構わずナンパする習性があるようで、女性にもモテ、家には常に違うガールフレンドが出入りしていた。どの女性も感じの良くきさくなタイプだったので、私は家にいるだけで色んな女の子としゃべれるのでラッキーだったのだと思う。
ベンはギターが上手で、毎日のようにリビングでギターを弾いていた。私の部屋に出たゴキブリをいつも率先して退治してくれたりと、弱冠23歳にしてとしても便りになる好青年だった。中国で勉強したという英語は、相当レベルが高く、UTSの語学学校時代、成績一位で卒業している。一度ベンの書いたレポートを見せてもらったのだが、そのボキャブラリーの多様さと表現レベルの高さに驚いたのを覚えている。
一時期、どうやらベンが私とアナンタの食べ物を(しかも作り置きしてタッパーに入れてある料理などを)結構な頻度で無断で食べているということが問題になったことがあった。最初のうちは、あれっ○○がなくなってるなぁ〜。ぐらいに思っていたが、それが毎日のように起こるようになったので、アナンタがベンを招集し、3人で家族会議が開かれることになる。
先生が本業であるアナンタは、こんこんとベンに対して説得を始める。決して感情的になるのではなく、相手を非難する訳でもなく、落ち着いて話をするアナンタを立派だなぁと、私はただただ感心していた。最初は照れ隠しのためかヘラヘラと聞いていたベンも、最後は真顔になって「分かった」と言って、私達に謝る。その日からベンは改心したのか、無断で食べ物を取る行為をしなくなり、変わりに私達に料理を振る舞ってくれるまでになった。
幼少期貧乏な生活をしていて、ホームレスも経験しているアナンタは時々その当時の話をしてくれた。両親が離婚して、母親がギャンブル中毒になり、今でもアナンタに時々お金を借りに来るということも。人が好きで、ポジティブで強いエネルギーを持っているアナンタ。人気者で太陽みたいな存在のアナンタも、時々「陰と陽の陰に埋もれたくなることがある」というようなことを言っていた。
一方、裕福な家庭に生まれたベンの母親は、政府関係の仕事をしている有能なキャリアウーマンのようで、人付き合いも上手で人脈も広いそうだ。彼はそんな母親に、認められたいというコンプレックスを常に抱えており、両親の期待を背負ってオーストラリアに来たものの、当の本人は将来の目標がいまひとつ見つからず、迷子になっているのだと言う。そして「常に自分が誰かの借り物の自分であるような気がする。オリジナルの自分を創りたい」とも口にしていた。
私も目に見えないものを求めて、一旦迷子になるために オーストラリアに来たようなものだ。そして、シドニーに来てしばらく経つと、自分の中にあるドロドロした感情や不安が顔を出す。そんな時はいつもアナンタから「人生は(マイコが考えているより)もっとシンプルだよ。自分で複雑化して苦しむな、感情のワナにはまるなよ」と言われた。そして、「何かあったらオレに話してよ」と言ってくれたアナンタの言葉が、本当に心強かった。アナンタとベンには時に感情をぶつけてしまい、彼らを困惑させてしまったと思う。環境の違うもの同士、抱えるものも全く別々ではあったが、私達はそれぞれの生い立ちや将来のことを話した。この時間は本当に貴重であったと思う。
―学校生活
学校はELSIS。ここも感覚で気に入って、ケンブリッジのクラスに入りたかった。クラスのスタートは半期に一度である。そのスタート日がちょうど来週に控えていたこともあり、何かしら運命めいたものを感じて、ケンブリッジのクラスに入講したいという気持ちが高まる。入講テストで無事に合格した私は、迷わずELSISに行くことに決めた。
EISISはパーティ好きなヨーロピアン、ブラジル人の集まりという事前情報もあり、そんなイケイケの集団についていけるか内心ちょっと不安だったが、クラスメイトは落ち着いた人が多く、知的な大人という印象を受けてほっとした。
クラスメイトは全員で9人。チェコ・スロバキア、イタリア、スペイン、ドイツ、ブラジル。ヨーロッパ系のクラスメイトは初めこそクールでとっつきにくい印象があったが、仲良くなると途端に話しやすくなり、ユーモアのセンスも日本と少し似ている部分もあり(特に東欧系)、一緒にいて面白かった。
また、私は授業中あまり目立たないけれど、酒を飲むとお調子者になるところが良い、日本人なのに酒が強い方だと褒められ(?)、特に酒が強いという自覚はなかったが、クラスメイトで飲みに行くといつも最後まで残るのはチェコ人と私だったと記憶している。
先生は陽気なオージーのJamesとスコットランド出身の堅実派Steaven。この二人のバランスは最高だった。古典的な小説からの引用で、ボキャブラリーの勉強をしたり、時には教室のスクリーンでLife of Pieの映画を観たりと、知的好奇心とやや脱力した感じの面白さで毎回授業は展開していた。
時々、自分の英語能力の限界とモチベーションの低下に行き詰ることもあったが、ケンブリッジのクラスを受けて本当に良かったと思っている。
終盤はもうすぐクラスが終わってしまうという寂しさと、試験目前のみんなの共通した緊張感からかさらに団結力が高まり、卒業式ではクラスメイトの何人か泣いていた。
―仕事について
サブカルチャーとポップアート、そして異文化をごちゃまぜにしたようなNEWTOWNの雰囲気が好きで、仕事するなら絶対ここがいい!と思っていた。その為、NEWTOWN中をあてもなく奔走し、英語はなんとかなるだろうと高をくくり、経験もないくせに敷居が高めのレストランやバーを手当り次第にトライし、あっけなく玉砕していた。
またGumtreeという便利なサイトを利用することもなく、すべては店に直接交渉体当たりという変な意地を張っていたことも反省する点として挙げられる。ただ、それにより度胸はついてその後の仕事探しで効果を発揮することは度々あったので、良い点もあったと思う。
そんな無謀な行動に今思い出しても恥ずかしい限りだが、渦中の本人はそれしか見えていなかったので仕方がなかった思うことにしている。また、3ヶ月も経つ頃には結構なNEWTOWN通になり、近隣にあるErskinevilleというマイナーなスポットまで開拓していったので、それなりに楽しいこともあった。
その一方で、シドニー生活はことごとく散財しており物欲で満たそうとしているなんて、これじゃあ日本でOLをやっていた頃となんら変わりなく、異国でただ金をばらまいているだけのような状況に嫌気がさしてきたのもちょうどこの頃だった。また仕事面だけではなく、私のメンタル面も大分しけってきていた。そういうわけで私は学校が終わるとほぼ同時に、逃げるようにシドニーを出た。
◆ラウンドの始まり 西オーストラリアへ
―ジンベイザメと泳ぐ旅
ふと手帳を開けると、日本で書いた“オーストラリアでやりたいことリスト”の中に「ジンベイザメと泳ぐ」というのが目に飛び込んできた。自分でも書いたことすら忘れていたが、なぜか無性に気になる。ネットで調べてみたところ、ちょうどシーズン中ということで、私は迷わず西オーストラリアにあるExmouthへ向かった。早朝5時に駅で空港行きの電車を待ちながら、何か新しいことが始まりそうな予感がしていたのを覚えている。Exmouthへ到着した日は激しい雨が降っていた。今の私に時間の限りは無い。着いてすぐ宿を探すつもりだったが、天気が回復するまでのんびり待つことにした。たまたま隣にいたオージーの女性と話をしていたら、どうやらその女性は車でこちらに向かっている旦那さんを待っているそうで、「雨がすごいし、宿まで乗っけていってあげるわよ」と言ってくれた。シドニーでは感じたことのなかった、偶然出会ったローカルの人たちの優しさというものに触れ、早速感動する。宿が決まってなかったので、周辺のバッパーとキャラバンパークを一緒に下見してくれ、私はその夫婦が以前宿泊したことがあるというオススメのキャラバンパーク(バッパー宿泊施設もあり)にした。別れる時に、「私達も昔二人で色んな国を旅したのよ。あなたと話していて、それが蘇ってくるようで楽しかったわ!」と言ってくれ、その親切な夫婦にお礼を言い、私達はハグをして別れた。
2日目からは天気が回復し、翌日のツアーを申し込む。ツアーはちょうど残り1席と言われ、またここでも運命めいたものを感じた。その夜に同じキャラバンパークに泊まっているドイツ人カップルと仲良くなり、Staircase to the moon月への階段(月の光が海面に反射して、階段のようにみえる)を探しにドライブへ行くから一緒にどうかと誘ってくれた。月への階段は、てっきりBroomという場所でしか見られないものと思っていたので、見れたらいいな、ラッキーだなという気持ちでジョインすることに。そして車は走り出すが、正確な場所を知っているものは誰もいない。取りあえず海を目指そう、ということだが、携帯の電波もつながらなくなり、皆の野生の勘だけを頼りに車を走らせる。街頭もない真っ暗闇なので、自分達が一体どこに向かっているのかすら分からない。もう見れないよな…とおそらくそこにいる全員があきらめかけた時、私達は前方左側に光る球体とその下にうっすらと光が反射しているのを見つける。やっと海を見つけたのだ。
私達は海辺に向かって車を走らせ、そして到着すると飛び出すように車を出た。目の前の海には光のイリュージョンともいえる、月の階段があった。しかもこの日はちょうど満月で、月へと延びていく強い光が海面に反射されている。私達は砂浜に座り、しばらくの間その 景色を眺めていた。そして、帰りの車の中でドイツ人カップルから旅の話を聞いていたところ、「北西にあるカリジニ国立公園は是非行くといいよ、とにかくオススメ」と言われ、私の心の中でぼんやりと次の目的地が設定された。
翌日。ジンベイザメツアーは15名ほどの少人数で、小学生ぐらいの子供の家族連れやカップルが多く、とても和やかなムードだった。移動中も船の上でも、終始温かい雰囲気が漂っていたのを覚えている。
そして、待ちに待ったジンベイザメは想像を超える美しさだった。動物に対して、美しいという感情を持った初めての体験だったと言える。確か私が小学校4年生の時、大阪にある海遊館で初めてジンベイザメを見て、その大きさと 水槽いっぱいに優雅に泳ぐ様子に感動したことを思い出す。あの時10歳だった私が大人になった今、こうしてジンベイザメと一緒に並んで泳いでいるのだ。
また、このツアーで私は一人の台湾人と出会った。ちなみに彼は後に私のパートナーとなる。聞けば彼はこの後、友達と車でカリジニ国立公園にキャンプに行く予定なのでよかったら同乗しないかと言う。昨日願っていたことが、今日実現するなんて!ツイてるなーと思いながら、私は彼らと一緒に翌日荷物をまとめてカリジニ国立公園へと向かった。
道中はこれぞオーストラリアのOutbackといった、地球の果てのような乾いた土がどこまでもつながっていく風景。何時間も代わり映えの無い平坦な風景なのに、無性にワクワクするから不思議だ。7時間のドライブを経て、私達はカリジニ国立公園近くの小さな町Tom Priceに到着。この町のキャラバンパークでキャンプを張って、これから3日間寝泊まりをする。
翌日はNameless mountainに登り、初めての登山を達成する。
キャラバンパークではシャワーの蛇口を回し過ぎて、お湯が大放水するというハプニングで着替えがすべて水浸しに。初めてのキャンプ生活で戸惑うこともしばしばあったが、この場所でキャンプと登山の面白さに目覚めることになる。カリジニ国立公園へは4WDの車かバスが必要な舗装されていない道路の為、ツアーで参加した。前日に自力で登った感動が大きくて、ツアーで参加したカリジニ国立公園は思ったよりも感動は得られなかった。それでも太陽が水面に反射して描かれるマーブル模様のような泉や、赤い岩と青空のコントラストは見事で、溜息がでるほど綺麗だった。
―Carnarvonでエビ釣り漁船に乗る
カリジニ国立公園のキャンプも終え、台湾人の友達は2人とも帰国を控えているためPerthに戻ることに。私はTom PrinceからPerthに向かう途中で適当に町で降ろしてもらうことにした。
そして、偶然降り立ったカナーボンという町が、色んな意味でラウンドの本当の始まりだったように思う。
バッパーに着いた翌日の朝、オーナーが「あんた、エビ釣り漁船に乗りたいか?」と突然聞いてきたので、思ってもいないチャンス到来にテンションが上がり「おお!乗りたいです!」と言い、私は二つ返事でオッケーした。
出発は約2時間後の昼12時。参加者は同じバッパーに泊まっている、ちょっと弱気で心配症のフランス人ヴィンセントと私の2人だ。 必要なものを持ってリビングに集合と言われ、近所のスーパーで買い出しに向かう私達。
ヴィンセントはスポーツ用品店で上下フリースを買い揃え、サングラスまで購入するという気合の入りようだった。私たちはとにかく船酔いが心配だったので、2人で種類の異なるタブレットを1箱ずつ購入することにした。
乗り組み員は私達の他に、スッキッパー(船長)と、漁師のパトリック、ダニエル、ドウェインの6人。夕方の4時起床、翌日の朝10時まで働くという昼夜逆転パターンで10日間の航海だ。その中で私の仕事は、釣り上げられた魚介類の中からエビの仕分けと漁師達の食事の準備だった。
船に乗り込むと、既にほろ酔いのパトリックがビールを片手に登場する。私もビールを勧められたが、船酔いの心配もあり断ることにした。夕食の時間になり、私は船の中にキッチンへ向かう。料理中、早速揺れがひどくなってきた為、右手はフライパンに、もう片方の手は倒れないように取ってをつかんでいた。そうでなければ転がってしまいそうだった。やっとの思いで仕上げた初日の料理は、中華風の炒め物とライス。
まず食べ始める前に漁師達は、料理に大量のチリソースをぶっかけていたのだが、それは思わず目を疑う量だった。それ以外にコーヒーを入れるのも私の役目だったのだが、小さ目のマグカップに大匙3杯の砂糖を入れてくれと言われ、味覚が完全にイカれていた。
この先10日間、味覚が崩壊したメンバーと共におとどけすると思うと少々気が重くなったが、一度乗りかかった船なので後には引けない。
それに初日は緊張と興奮も交じっており、夕方のデッキで見た夕日の美しさや間近で見るイルカの群れに感動したりしながら過ぎていき、これから恐ろしい船酔いに悩まされることになることになるとは露とも知らず、1日目が無事に終了し私は寝床に着いた。
起床時間の夕方4時を過ぎ、6時近くなっても誰も起きる気配がなかったので、うとうとして目を閉じた数分後、突然暴動のような勢いでドアをノックする音で、私と同室のドウェインは文字通り飛び起きた。スキッパーが他の漁師の部屋も続けて叩く音が響き、全員寝過ごしたということが判明する。
そして体調に異変が現れたのは、早くも2日目だった。
初日は船酔いがなかった為、油断して酔い止めを飲み忘れたと気が付いた時にはもう遅かった。吐き気と戦いながら、なんとか朝ごはん(時間帯的には夜ご飯)を作り終えた時にはもう気持ち悪さがピークに達していた。
それでもエビの仕分けの手伝いをしなければならなかった為、デッキに出て行った。外の寒さで少し気分がさっぱりしたのと、エビの仕分けで集中している為か吐き気が若干和らいでいくのを感じだ。
その時、今まで味わったことのない、小さくて鈍い痛みがゴーンという感覚で全身を走った。何かに刺されたらしい。ゴム手袋を取ると、刺された指先から血が流れている。そして、徐々に指がしびれて脈を打つごとにズキズキと痛む。これは全身に毒が回っている!!とパニックになった私は、隣にいたドウェインに訴えた。すると痛みの犯人はストーンフィッシュという魚で、しびれるのはバクテリアのせいだから安心しろと言われ、ミントのキャンディーをくれた。
とりあえず毒では無いということを確認して、お菓子でなだめられた私はその後も悶々とする気持ちの中作業を続けた。そこで私は仕分けの際に、ヒトデを熊手替わりに使うことにした。ヒトデには悪いが、こうすれば直接ストーンフィッシュに触らずに済む。しかし、私がヒトデを使って何度も掻き分けているところを見たダニエルが、作業が遅くなるからヒトデなんか使うな、流れてきた海産物を一回ヒトデでザーッとならしてお終いだと言い私のヒトデは没収された。ここで私のヒトデ作戦はあっけなく敗退することになる。
それから注意はしているものの、眠気との戦いもあり朦朧とする意識の中で何度がストーンフィッシュの攻撃にあい、その度に半泣きになっていた。
時々スキッパーが操縦席から下に降りてきては、怒鳴り声をあげ、ひたすらFuckを連発している。この人は一体何にそんなに怒っているんだろうと、私には終始疑問であった。そして始めこそ、この罵声に少しおびえていたが、オージーアクセントが強すぎて聞き取れないこともあり、しばらくたつとただのノイズぐらいに感じるようになる。そのノイズ以上の大音量で、明け方までマリリン・マンソンの音楽が流れており、熟睡できそうもない空気の中で寝床についた。
そして三日目にはとうとう起き上がれないくらい船酔いが悪化し、トイレとベッドを往復するだけの廃人と化す。何も食べることが出来ず、胃の中のものはすべて吐き、その後も胃液を吐き続けて本当に苦しかった。同室のドウェインが気遣ってくれ、彼が運んでくれたフルーツなどを食べてなんとか生息していたように思う。時々様子を見に来てくれたドウェインが私に「こんな辛そうで可哀想だよ…」という言葉に続けて、「僕も本当はこんな過酷な仕事をしたくない。でも行くあてがないんだ…。」と言った。その話を語っているときにまじまじと彼の顔を見たが、36歳とは思えない程深く刻み込まれたシワと、それに不釣り合いなぐらい透き通ったガラスみたいな瞳が印象的だった。
四日目に私は陸に戻されることになり、私の短いようで長かった船上生活は終わった。ヴィンセントは船酔いこそなかったものの、「もうこんな場所にはいられない」といい、私と一緒にリタイアすることに。彼から聞いたところによると、漁師達は何やら粗悪なドラッグをやっており、テンションが終始おかしかったり、少しでも休んでいたら、殴るぞと脅されたりと男だけの現場は更に過酷だったようだ。
港に戻され、バッパーに帰った後もヴィンセントは相当うなだれており、「僕は今までで一番バカなことをしてしまった」と嘆き、「でも、マイコの作ったポテトサラダが美味しかった」という言葉を残して、早々と荷物をまとめて出て行ってしまった。
私は、無事に沖に戻ってこれたという安堵感と、何やらちょっと珍しい体験ができたんじゃないかという軽い興奮で、回りにいる旅人たちに今回起こったことを延々と話していたら随分と気が楽になった。そして、その日の夜はとにかくよく眠った。
―初めてのファームジョブ
朝になって私は、友達の友達が前に働いていたファームの連絡先を教えてもらっていたことを思い出す。その人曰く、時給ではなく歩合制のイリーガルファームで、あんまりオススメはしないけれど…という点も覚えていた。
こうゆう場所がクソファームって呼ばれるのかなぁと考え初めたが、仕事が欲しいのと、それに俗に言われるクソファームってどんな所だろう、というしょうもない好奇心もあって、私はそのオーナーに連絡を取った。自分の目で見るまで納得できず、ついつい試してみるたちなのだ。
それはベトナム人オーナーの経営する、トウガラシファームだった。
トウガラシの中でも小さい種類のチリペッパーだったので、そのバスケットを1箱埋めるのも気の遠くなる作業だった。その上私は相当作業が遅かったようで、結局この日の給料は一日中働いて50ドルであったと記憶している。
また、この場所は市街地から20分車を走らせたど田舎にあり、見渡す限り畑でOptusは電波が入らなかった。寝泊まりする場所はボスが用意してくれると言っていたが、実際にスタッフ用の寝床はなく、普段奥さんと子供用の寝室という洗濯物に囲まれた部屋を借りることになる(奥さんと子供は家をしばらく空けているということだった)。
晩御飯の時間になり、キッチンではボスが手慣れた手つきで料理をしており、テーブルには次々にベトナムっぽい料理が並べられていく。私と同じファームで働いている香港ボーイに「夕食一緒に食べるぞー」と言い、私も嬉しくなって夕食の準備を手伝った。ベトナムでは基本料理という鶏の足がなんともグロテスクな形で(鶏の爪先部分のしわしわの皮の感じ)抵抗があったが、生春巻きやベトナム風煮物、肉まんの皮だけのようなパンは美味しかった。久しぶりに食べたアジア料理に、私の胃袋も喜んでいるのを感じた。
しばらくすると、ボスの知り合いで近所のトマトファームで働くマレーシア人と香港人カップルも合流する。ボスに勧められるままに、ビールも飲み、楽しい宴会気分だ。ボスのカラオケショーが始まり、ベトナム語で歌うボスのカラオケにマレーシア人が音頭を取り、私達も手拍子で合わせながら、カラオケは国境を越えるという言葉が頭に浮かんでいた。
そんな楽しい酒を酌み交わした翌日、あろうことに私はあっけなくクビになった。理由は作業が遅い、そして車も持っていないし、明日ボスの奥さんと子供が帰ってくるから私の寝床もなくなる、という。またも行き場を失った私はまた同じバッパーに帰ることに。何度もこの場所に帰る度に、心の拠り所のような存在になっていた。しかし毎日の宿泊代がばかにならないこともあり、そろそろシェアハウスに移ろうと計画する。そしてExmouthで知り合った台湾人の友達の紹介で、台湾人男女6人が住んでいるシェアハウスへ移動し、また仕事探しを始めることになる。
―チャイニーズカフェ
カナーボンはメインストリートが1本しかない小さな町なので、周囲に店は10件もなかったが、ほぼすべての店にレジュメを配ることからスタートした。そこからは行動範囲を広げ、自転車を借り1日10時間かけて近くのファームを回ることに。
自転車で移動中に横を走る車からやじを飛ばされて、ビックリしてこけそうになったり、番犬に追いかけられたりと情けない上に収穫が無い不毛な時間が過ぎていった。仕事を探し始めて1週間が経とうとした時、以前レジュメを渡したチャイニーズカフェから連絡がある。
正直言って、チャイニーズカフェかぁ〜というパッとしない気持ちはごまかせなかったが、早く仕事にありつきたいという想いの方が勝っていたので、給料を少し上げてほしいとオーナーに話をし、週$750で交渉は成立した。ここでの仕事は、コーヒーをつくる、50種類ほどのアジア料理(チャーハンやラクサなど)の食材が表のショーケースに並んでいるため、注文をとってすぐ必要な具材をボウルに盛ってシェフまで運ぶという、単純だが覚えることが多かった。
勤務時間は朝の8時半から夜の9時まで(途中ランチとディナーの間に2〜3時間休憩)で週7日勤務だ。休みがない理由は、中国人マネージャー(兼シェフ)と中国人シェフ1人とフロントスタッフ(兼バリスタ・レジ打ち)3人で構成されていたため、1人でも欠員すると死活問題なのである。それならもう1人でも雇って、シフト制にでもすればいいのにと色々と思うことはあったが、謎だらけの店でマネージャーに言ったところでどうにもならなさそうだったので、おとなしく従うことにした。
マネージャーとはよく衝突し、喧嘩した。年も近く、お互い単純な性格でキャパが小さいという似たような性格のためだったように思う。客には無愛想だけれど、一緒に働いている私達には気遣ってくれたり(夜道は危ないからと仕事の後は毎日家まで送ってくれた)。作業を早くやれ!と急かされるのだけれど、それは空き時間をつくって休憩させてくれるためであり、わざわざ裏から椅子まで持ってきてくれ、座って休むよう命じられた。仕事開始時間も、いつも5分前に到着して玄関で待っていたら、「みんな10分遅れてくるんだから、おまえも10分後に来い」と言われ、優しいんだかなんだか。そしてもっと楽に働けとよく言われたものだ。
陳列している売り物のソフトドリンクも寿司ロールも食べ放題で、さらに昼・夜はこってりした中華料理付き。
こうして私はこの場所で、自分史上の最高体重を記録することになる。ちなみに無休で食事付きだった為、特にお金を使う理由も時間も無く、オーストラリア滞在中で一番貯金額が多かったのもこの時期だった。
そうして1ヶ月が経とうとした頃、オーナーの希望で、私よりも長期間働ける人(香港人)が知らぬ間に採用されていた。ある日突然、マネージャーから「お前はそろそろ辞めることになるだろう」と予言者のように告げられ、私はしばし憤慨したが、ほぼ同時期に次の目的地が決まったので、一応は円満退社だったのだろう。コーヒーの淹れ方を学び、マネージャーと喧嘩しながら過ぎていった短いようで濃いチャイニーズカフェでの1ヶ月は幕を閉じた。
―シェアメイトとの思い出
台湾のシェアメイト達は、皆本当に温かかった。時々天然な所が可愛くて、まっすぐで、友達想いのイヴァ、面倒見がよくて、いつも優しかったフィフィ, 最年長のため一家の大黒柱のような存在だが、シェアメイトの女性たちには頭が上がらない、お人よしで心優しいマックス、お調子者で物まね好きなライアン、シャイボーイのジェリー、日本語が達者で料理が上手な男の子だけれど皆のお母さん的存在マーク。
夜ご飯は、毎晩皆で大きな丸テーブルを囲んでの団欒だった。食卓にはイヴァとフィフィが仕事場のファームからもらった新鮮な野菜を使って作ったマーク特製のおいしい台湾料理が並ぶ。私はチャイニーズレストランから持ち帰った寿司ロールや春巻きを並べて、こんな風にみんなで分け合って食べる食事って幸せだなぁと、しみじみと感じていた。
私がチャイニーズレストランで、それほどストレスも感じることもなく無休で1ヶ月働き続けることができたのは、シェアメイトの存在があったからであろう。今思い返しても、温かい感情が湧き上がる思い出が一番多い。
また隣の家にはルーシーとい名前のとても人懐っこい犬がいた。もと救助犬だったというルーシーは、優しい目をしていた。飼い主のおばさんは腰が悪かったので、散歩に連れて行くことができず、ルーシーは家の前の庭で遊んでいた。広い道を走り出したかったのだろう。飼い主のおばさんの了解を得て、時々ルーシーと散歩に出かけたり、私が働いているチャイニーズカフェまでついて来てしまい、1日限定で看板犬をしたこともあった。
1ヶ月経つ頃、Exmouthで出会った台湾人の友達からWWOOF先を教えてもらう。場所はVictoria州にあるアートギャラリーだ。ホームページを見たところ、もうこれは行くしかない!と感じる。私がアートに興味があると知っている彼は「是非行ってみなよ」と言う。ただ、突然のことだったので、私が少し躊躇していると、「絶対行くべきだ」といつもにもない強い口調に背中を押され、私はすぐにオーナーに電話を掛けた。電話口に出た女性(オーナー夫婦の奥さんだろうか)はとても感じがよく、私が今Carnarvonにいるということを告げると驚いていたが、私の出発準備ができるまで数週間待ってくれるという。私は来週には出発できることを告げ、採用が決まり急いでPerthまでのバスとMelbourneへ行きのフライトを予約した。
Carnarvon最終日。「マイコは1ヶ月無休で働いていたから、Carnarvonを一緒に観光できなかったよね」と言って、イヴァが撮ったCarnarvonの美しい夕日や海の写真の裏に、シェアメイト達一人ひとりがメッセージを書いてプレゼントしたくれた。思いがけないプレゼントに、胸が熱くなる。
さらに、長時間のバス移動でお腹がすくといけないからと言い、イヴァが朝からエッグタルトを作ってくれていて、私に持たせてくれた。ありがとうの言葉では足りない程、私の気持ちは溢れていた。この感謝の気持ちをどうやって伝えたらいいのだろう。「また絶対会おうね」そう言わないと、本当に寂しくなり泣きそうだった。
バス停には見送りに来てくれた、シェアメイト達とルーシーもいる。シェアメイトの皆が、ルーシーの飼い主のおばちゃんにお願いして、連れて来てくれたのだ。シェアメイト達とルーシーに見送られながら、私はCarnarvonを出発した。
もし予備知識があったら、このCarnarvonという、仕事が少なくて悪名高い場所にはいくら好奇心の強い私でも踏み入れなかっただろう。そう思うとなんの情報もなしにたまたま流れついて、転がり回った生活のなかに素敵な出会いや経験があり、思いがけない宝物を見つけたようなそんな気がした。
◆WWOOF体験
―森の中のアートギャラリー 陶芸家のオーナーとの出会い
10時間のバス移動を終え、Perthに着いた。そしてPerthからMelbourneへ飛び、そこからバスに乗って、オーナーとの集合場所であるGeelongへと向かう。 夕方の6時にGeelongに到着し、西オーストラリアとの気候の差を肌で感じながらしばらく待っていた。そこに颯爽と現れたオーストラリア人の陶芸家のオーナーGreame(グレム)はちょっと長めの銀髪を1つに束ねていて、カッコいい仙人という印象だった。最初の自己紹介は「はじめまして。グレムと言います」と日本語で挨拶をしてくれたのを覚えている。更に話していく中で、グレムはかなりの日本好きで何度も日本に訪れていることを知る。日本の捕鯨問題について聞かれたり、日本のイルカ漁に対するドキュメンタリー映画について話してくれたり、その中でオーストラリア人の自然観ってやはり日本と違うんだなぁと感じ興味を持った。もっと勉強したい!という知的好奇心がムクムクと湧き上がり、早くもグレムのことを師匠と呼びたくなる。
そして車を走らせること1時間半。森の中にある煙突から煙がモクモクと立つ、童話に出てきそうな素敵な家の前に到着する。そこで、グレムより20歳年下の笑顔が素適な美しい奥さんと、ここで8ヶ月WWOOFをしている韓国人夫婦が温かい雰囲気の中、迎えてくれた。
韓国人夫婦は二人とも私と同じ歳で、新婚旅行でオーストラリアにワーホリに来たというツワモノのジェイとダヒ。ジェイは自我が強くて頑固な一面もあるが、面倒見が良い兄貴肌で頼りになる存在だった。ダヒは料理が上手で優しくて、聞き上手な女の子。私の中で理想のお嫁さんだ。
ディナーをごちそうになった後、その時はWWOOF専用の家にはその夫婦が住んでおり、あと1週間程で別の場所へ仕事を探しに移るということで、それまで私は特別に宿泊施設に泊めてもらえることに。ベッドもかなり上質のもので、この日がオーストラリアに来て一番眠りが深かった夜と言える。宿泊施設は全部で5棟あり、その1軒1軒が平屋の古民家のような作り、ハス・ユメ・ヤマ・ハナ・ツキと日本語の名称がついていた。中のインテリアも、玄関の廊下から靴を脱いで畳にあがるスタイルで日本好きなグレムのこだわりが伺える。まず、作品造りのためのスタジオから始まって、アートギャラリー、隣接するカフェ、そして宿泊施設へと展開していったのだそうだ。
この広大な施設がグレム一人のアイディアで現実のものになったのだ。その話を聞いた時には、魂がふるえたのを覚えている。
また、カンガルーが敷地内の庭に遊びに来たり、ある時は朝起きたら家の前を歩く野生のコアラとの遭遇したり!自然が目の前を、当たり前のことのように通り過ぎていくことに感動を覚えていた。
仕事内容は日によって違っていて、カフェを手伝ったり、ハウスキーピングをしたり、グレムの創作活動のお手伝いなど。憧れていたローカルカフェがWWOOFFという形で実現し、私の心はときめいていた。
本格的にコーヒーの作り方を教えてもらえたことと、なによりお客さんと会話ができることが一番の楽しみだった。アートに興味を持っているお客さんが大半で、その中でも日本好きな人の多さには驚いた。話し始めると、話の締め方がよく分からず長話になってしまい、奥さんによく注意されたものだ。
数ヶ月が経つ頃、二人のシェフのうち一人が一身上の都合で繁忙期を前にして辞めることになり、WWOOFERの私達もキッチンを手伝うことが多くなる。キッチンで野菜を切ったりピザ生地を作ったり、客が来ればフロントで注文取り、時にはコーヒーを作り、時間を見計らってハウスキーピングをして、というマルチな内容になった。私は要領が悪いためか、奥さんからよく「Quick!Quick!」とプッシュされ、その度に嫌な気持ちになっていた。
グレムとの仕事は海辺に薪を拾いにいったり、陶芸用の粘土をこねたりと(陶芸家は重労働であることを知る)大抵が力仕事であった。私はいつもグレムと仕事をするのを楽しみにしていた。グレムのことが本当に大好きだったのだ。ユーモアがあって、日曜大工が好きで水道管の修理も自分でしてしまう、魔法使いのオジサンのような人。
グレムは日本が好きで、結構な日本通だった。グレムの日本に関する質問で、私が答えられないことが多々あり、私が本当に日本人なのか疑いを持ち始めたグレムは、私のことを「カンボジア人」と言うようになる。実際に知り合いや身内の人に私を紹介する際、こちらはカンボジア人の〜と言われるので、私はいつも慌てて訂正していた。そして毎日のおいしい賄い料理に更に体重を増していた私は、グレムから日本語で「太っちょ」と呼ばれるようになり、いつしか私は「太っちょのカンボジア人」となる。
―窯炊き、野外映画祭、ヌードショーと日本国総領事
私が滞在中の約4ヶ月の間、様々なイベントが催された。まず、1年に2度行われるという展覧会出品用の陶芸品と彫刻の窯焚きで、日本製の陶器用の窯が使用される。約1週間、グレムやその知り合いの人が交代で夜通し火の番をして、私も窯に入れる薪を割ったり、火の番の手伝いをした。夜ご飯も窯を囲んで皆で食べる。小さなお祭りのような、特別な夜という雰囲気が楽しい。
そしていよいよ窯の中から作品を取り出す日−。
グレムの作品以外にグレムの友人達も各々の作品を窯に入れており、私も箸置きを作らせてもらい、一緒に窯の中に入れていた。次々に運び出されるグレンの作品に歓声があがる。しかし更に一つ一つ作品を取り出していくにつれて、不穏な空気が流れ込む。どうやら、グレンが思っていた通りの色合いが出せなかったようだ。しかも作品の何点かは、温度調節を誤ったことによりヒビが入っている。もちろん誰かを責めているわけではないが、その時初めてグレムの怒った顔、芸術家の顔を見た。ギャラリーに運ぶ際には「落っことして割ったら殺すぞ!」と冗談だと思うが結構本気で言われていたので、ヒヤヒヤしながら運んだ。30数点ある作品を運んで、無事に展示が終わった時は、皆ほっと胸をなでおろした。
展覧会のオープニングセレモニー当日。今回の展覧会の出資をされたという、メルボルンにある日本領事館の総領事も招待されていた。一番乗りで現れた客は、その総領事の方だ。グレムに紹介されるが、総領事の方と日本語で一体何を話して良いのか分からず、一言二言で会話は終了する。ちなみにグレムは総領事の方のために、手作りの陶器の皿をプレゼントする予定で、渡す際に日本語で「つまらないものですが、どうぞ」と言いたいというので、直前までグレンにその日本語を教えていた。私も、グレムの口から堅い日本語のフレーズが出てくるなんて、結構面白いんじゃないかと思い、その総領事の方の反応を期待する。そして後からグレムに「どうだった?」と聞くと「全くウケなかった」と少しがっかりしていた。グレンのジョークは日本国総領事にウケなかったが、展覧会は大変盛り上がり、大盛況の中幕を閉じる。後日地元の新聞にも記事が小さく載っていた。
お次はFestival of performing artsという年に一度開催される、町をあげてのイベントがやってくる。町の中心街、海辺の大きな広場には鮮やかなサーカスのテントが張られ、お祭りムードだ。ここのアートギャラリーではヌードショーのディナーショーが行われるということで、私はドキドキしていた。約1週間前から準備が始まり、お皿の数を数えたり、ワイングラスを一つ一つ磨いたりとしばらく地道な作業が続いた。
そして当日−。
オーストラリアで有名な元ストリッパーということで、チケットは完売の満員御礼となる。私達は50人分の料理を運んだり、ワインを注いだりと忙しく動き回っていた。一段落して客席を覗いてみると、ステージは元ストリッパーの女性が髭ヅラで登場したり、突然ゴリラのかぶりものをしたりと、お笑いの要素が強かった。
想像していたヌードショーとは大きくかけ離れていたが、有名な元ストリッパーの体を張った演出に感服する。また、客層が40代から50代のカップルが多いことも驚いた点だった。仮に日本でお笑い風ストリップショーが行われたとしても、客の半数が熟年夫婦という状況は想像できないなぁと思い、この場で同時に異文化を感じたものだ。そんなことを考えているうちにショーが終わり、私達は片づけに追われることに。片づけの作業は夜中の12時近くまで続き、奥さんも「これが接客業の裏側よ」と言っていた。
さて、Artに続き今度はフィルムフェスティバルだ。町の至る所、映画館はもちろんのことホテルやレストランでも映画の上映会が行われる。このイベントも毎年一度行われるもので、その年ごとに上映される映画が選ばれるのだが、その中に邦画もあり、この年は『崖の上のポニョ』と『アウトレイジ』というなんとも対照的なセレクトだった。
ちなみにアートギャラリーで上映されたのは『Age of Consent』という60年代のアメリカ映画。敷地内の庭に巨大スクリーンを設営して、日が沈んでからの野外映画鑑賞会だ。訪れた客に出すための、ワインやビールなどの簡単な飲み物に加え、この日のためにレンタルした屋外用のコーヒーマシンも準備する。暗くなり、徐々に人が集まり、皆この小さなコーヒースタンドで温かいコーヒーやワインを注文していく。私達も始めはドリンクの注文を取ったり、ワインを注いだりしていたが、映画が始まり芝生に座った。11月でオーストラリアではもうすぐ夏を迎える頃なのだが、森の中の夜はまだ寒かった。スクリーンから少し離れた脇にこしらえられた焚火、小さなパラソルを付けたコーヒーマシン。それらが静かな森の夜に、ピッタリと寄り添っている。まるでその情景も映画のワンシーンのようだった。
ここに来て2ヶ月がたった頃、Exmouthで出会った台湾人の彼(この時に私のパートナーになる)が来て、ここで共同生活が始まることになる。ここからが歓喜に変わり波乱の幕開けだ。カラフルで楽しいイベントの裏には、せっかくの珍しい行事を純粋に心から楽しめていない自分がおり、それが自分でも不思議でしょうがなかった。
―量子力学とチベットのお坊さん
様々なイベントは実際にとても楽しかったし、豊かな体験をさせてもらったと思っている。しかし、私の心は日に日にもろくなっていく感覚だった。奥さんにミスを指摘され、感情的にまくしたてられたりすると、必要以上に落ち込む。生まれて初めて過呼吸になったのも、ちょうどこの頃だった。ちなみに奥さんは感情表現豊かで、温かくてとても素敵な方である。あれこれ注意されたのも、私に対するトレーニングであったと思うし、それに対して私が過敏になり過ぎていたのだと思う。
ある時、ほんの些細なことでパートナーとの誤解が生じ、ものすごい不安に襲われた私が、衝動的に3本あったワインボトルをすべて台所に向かって投げつけるという事件が起きた。壁一枚隔てた隣の部屋にいた彼は、物音を聞きつけて飛んできた。私は軽い興奮状態で、その時は感じなかったのだが視線を落とすと指から血が流れていて、カーペットに滴り落ちている。彼は散らばったガラスの破片を一緒に片づけてくれた。ふと我に返ると、感覚が徐々に戻って指先の傷が痛みだす。彼はその傷が綺麗にふさがるまで、毎日かかさず消毒をしてくれた。
そんなある日、「これを観るといい」と言って、グレムから一本のDVDを手渡される。それは“What the bleep Do we know?”というタイトルの映画で、私達はなぜ生まれてきて、どこへ行くの?という漠然とした哲学的なオープニング。一言でいうと“意識が現実を創造する”というスピリチャル系ドキュメンタリー映画なのだが、量子力学の観点からも説いているところがとても興味深かった。
そしてある時は、チベットのお坊さんの説法を聞きに連れて行ってくれた。グレムは熱心な仏教徒で、何人かチベットのお坊さんの知り合いもおり、グレム自身もダライ・ラマに会ったことがあるらしい。
説法を聞いた直後は、自分がきちんと自分自身の人生の中心に戻ってきた気がした。そして、グレムが私に言った「お前は考え過ぎる。すべてはお前の頭の中で起こっている」という言葉が頭の中を巡る。
自分でもよく分からなかった。自分の中に起きた心の異変であった。あんなに起伏の激しい自分自身を見たのはオーストラリアに来て以来、この時が初めてだった。取り乱したり、爆発した発端は本当に些細なことで、後から思えば、冷静になり、そしてどれだけでも寛大になれるのが不思議だ。
しかしその時は、免疫の無い私の抗体反応のように、頭や心ではコントロールできないものだった。ずっと昔から自分の中に存在していたであろう、甘えと、自分に自信が無いという不安と弱さが、統括されたのかもしれない。そんな部分をさらけ出した自分の前にいた人達との関係が、以前とは違う元には戻れない道を進んでいる感覚が、ただただ悲しかった。
環境が変われば、きっと私はまた落ち着きを取り戻す。パートナーと自分自身にもそう言い聞かせていた。この先も答えは分かっていたが、この場所に留まり続ける強さは持ち合わせていない。もともとWWOOFの後はタスマニア行きを予定していたので、オーナー夫妻にも一カ月前からそのことは告げていた。しかし、気持ちの面ではまたもや逃げるように、そして掴めそうな何かを期待して、今居る場所を発つことになる。
グレムとの別れは寂しかった。彼はずっと、変わらない態度で私に接してくれた。そして何度も私にヒントを与えてくれた。彼だけではなく、きっとそこにいた誰もが私を支えてくれていたに違いない。私は感謝とせつない気持ちを抱えて、パートナーと一緒にタスマニアへ旅立った。
◆苦楽を通して見たタスマニアの景色
―タスマニア島上陸
私達はMelbourneから、SPIRIT OF TASMANIAという船に乗り、12時間かけてタスマニアへ渡った。この船は本土からタスマニアへ車ごと移動する人達が主に利用するようであったが、私はただ単にこの船に乗ってみたかったのだ。
島に着いた日、あの時みた朝日。船から見たオレンジ色に照らされた小さな町と、澄みきった粒子の細かい空気。あの感覚を私はずっと忘れないだろう。
およそ200年前、オーストラリア大陸に初めて到達したキャプテン・クックの感動が少し味わえた気がする。
私達はレンタカーを借りて10日間タスマニア中をロードトリップする計画を立て、Devonportから出発し、壁画の町Sheffieldへ向かった。そして北西のStanleyへ移動しThe Nutという別名海の上のウルルを見る。Cradle Mountainは12月(オーストラリアでは初夏)なのに、雪がまばらに残っていた。頂上までのトレッキングに挑戦したが、みぞれが降りしきる中、雨具を装備していない状態で5時間も歩き続けた為、全身ズブ濡れになり、寒くて感覚がなくなってくる。結局6合目付近で引き返すことにした。夜は一段と気温が下がり、ありったけの衣服を着こむがそれでも寒い。K-Martで買った安物の寝袋しか持っていない私は、寒さとの戦いであった。
3日間の極寒キャンプが終わり、Chocolate factory, Cheese factory, Raspberry factory で寄り道をして、試食を堪能しながらLaunceston(タスマニアで2番目に大きい都市)へと向かう。Launcestonの市街地から徒歩10分程度の場所に、突如巨大な渓谷が現れる。渓谷の前には川が流れ、その手前にはフリーの屋外スイミングプールがある。川で泳ぐ者、芝生に寝転んで渓谷と川を眺める者、スイミングプールで泳ぐ者。皆が思い思いの格好で休日の昼下がりを楽しんでいた。Launcestonで一泊$17の格安バッパーを見つけて、そこに2泊することに。なぜか私達の他に泊まっている客はだれもおらず、貸切状態であった。そして安さの理由は、このバッパーはIrish Barの2階にあり、毎晩明け方5時まで演奏されるライブミュージックがバッパー中にも響き渡るというところにあった。
2日後、やや寝不足気味で出発したLauncestonの次はラベンダーファームへと向かう。しかしシーズンが少し早かったせいか、ラベンダーは7分咲き程度であった(後に見頃は1月〜2月ということが判明)。
その後、St Helensへと南下し、ふと目に着いたシーフードショップで食べた生ガキのおいしさに感動しながら更に下りColes Bayに到着する。海の前のキャンプ場でテントを張り、しばらく電気とお湯の無い生活に。最後の夜は、ちょっと贅沢しようとColes Bay近くで偶然立ち寄ったレストランが、感動的なおいしさだった。タスマニアは食べ物の質が高いと言われているが、あれは本当であった。
翌日、Coles Bayを出発し、私達は再び内陸へと車を走らせる。魔女の宅急便のキキが働くパン屋のモデルになったと言われている場所、Rossという町にいくためだ。そのパン屋さんは香港からの観光客が大勢詰めかけていた。モデルになったと言われれば、そうとかもしれないな、といった具合であった。店の番台には黒猫ジジのぬいぐるみが飾られている。ちなみにパンはとても美味しかった。そしてPort Arthurを巡り、Hobartに到着するといった旅のルートだった。
この10日間、目の前に展開される色鮮やかな景色に、私はただただ感動していた。自然が生きているってこうゆうことなのかなぁと。中でも特筆すべき場所は、まずStanleyから東へ数時間車を走らせた場所にあるRocky Cape National Park。誰も知らない楽園と呼んでもいい程、人が全くいなかった。パンフレットにもあまり載っていなく偶然通りかかった場所だったので、全く期待していなかった分感動が大きかったのかもしれない。自然の色でこれほどまでに多彩な風景を見たのは、これが初めてだった。
そして、タスマニアで一番美しい海岸と言われるColes Bayが見渡せるMt.Amosだ。
往復3時間のトレッキングは距離こそ長くはないものの、岩道が多く、後半は足場を探しながら急斜面をよじ登っていく(この岩場は大変滑りやすいため、雨天時や雨が降った翌日などは安全上トレッキングが禁止されている)。
下を見下ろすとその高さと斜面に恐れおののくのだが、頂上からの絶景はそこに到達するまでのその恐怖と疲労を、すべて帳消しにしてくれるほどの実力を持っていた。
そして最後に何と言ってもCradle Mountainだ。季節によって全く別世界を見せてくれる。最初に訪れた12月は山の端に雪が残っていた。天候が悪いと何も見えないが、晴れた日はどの景色を切り取っても絵葉書にしたくなるような、360°パノラマなのだ。また、山の天気は変わりやすく、麓からは全く予想もできない気候だったりするので、装備を万全にして充分な注意が必要だ。
晴れた日の2月にもう一度Cradle Mountainを訪れ、頂上までのトレッキングにリベンジする。往復8時間のトレッキングはMt.Amosを上回るアドベンチャー度だった。日本と同じ地球上とは思えない、別の世界に続いている道のようにも見えた。
最終目的地であるホバートへ到着し、10日間のロードトリップが終了する。またジョブハンティングという現実に向き合わなくてはならない時がきた。
―New Norfolk事変
Gumtreeで仕事を探し、手当り次第にレジュメを送ったところ、1件の場所から連絡がある。New NorfolkというHobartから車で20分程離れた場所にあるレストラン兼ホテルで仕事内容はウェイトレスとハウスキーピング。また、スタッフ用の宿泊施設もあるため、住み込みで働けるという。ただ、クリスマスと年末年始の繁忙期2週間のみの雇用で、給料のしくみは時給では無いことや、その他の労働条件についても電話で聞くも詳しくは教えてくれなかった為、怪しさを感じたが直接会ってみることになった。ヴィクトリア調のお屋敷風のホテルとレストランで、オーナーは老夫婦でオージーの旦那さんとイギリス人の奥さんだ。奥さんはヘンゼルとグレーテルに出てきそうなおばあさんでイヤミが多いが猫好き。旦那さんはアルプスの少女ハイジのおじいさんに似ていて、見た目は気難しそうだが実際はとても優しかった。そしてトミーという、頭が良く人懐っこい猫がいた。
一応ウェイトレスの経験がある私が採用され、パートナーの彼はそのレストランで夜2時間皿洗いの仕事をする変わりに宿代と食事があてがわれるというWWOOFとほぼ同じ条件であった。ちなみに目の前にはラズベリーファームがあるから、彼はそこで働くとよいとのことである。
また私の労働条件については「給料は週$400で、宿と食事付き。労働時間はその日によって変わる。暇な時に限り夜は働かなくて良い」と言われ、今ひとつ想像できないが、仕事が無いよりいいかという消極的な理由と、古めかしいお屋敷で働くのもちょっと面白いかなという軽い気持ちで、翌日からその場所にお世話になることにした。
私達の部屋は屋根裏にあり、猫のトミーもよく入り浸っていた。
猫と一緒に屋根裏部屋に住んでるなんて、魔女の宅急便みたいじゃん!と初めのころはワクワクしていた。それにおじいさんは、私達のことを子供たちと親しみを込めて呼んでくれ、嬉しくなる。
しかし仕事が始まると、厨房では夫婦喧嘩が繰り広げられており(きっとこれが彼らの日常の風景であろうが)、大変効率が悪く客数は少ないのに、毎回スムーズにいかないもどかしさがあった。それに悪い人ではないがマンガに出てきそうな意地悪ばあさんで、イヤミを言われたり感情的に怒られたりする度に私は疲弊する。それでも時々気遣ってくれたり、優しい面もあり、私もそうであるように不器用なだけなんだと思い直すようにし、良い部分だけを何とか必死に思い出すように心がけていた。
クリスマスイブと当日はとにかく忙しかった。
朝8時スタートで昼間に3時間休憩があり、終わったのは夜の11時。これで週$400かよ…という不満はやはり拭えない。その後もコンスタントに宿泊客やディナーの予約が入っており、1週間無休であった。それに加えやめておけばいいものを 少しでも稼ぎたくて、3時間の休憩時間中に目の前のラズベリーファームに行き、ピッキングの仕事をした。
ただ一日だけディナーの予約が入らなかった日があり、その日の夕方からHobartの港へヨットレースを観に連れて行ってくれたことは、今でもとても感謝している。
パートナーの彼からも「感情をコントロールしろ。ここにいるのはたった2週間なんだから」となだめられるも、おばあさんの前で労働条件について度々不満を漏らしてしまい、私達は徐々に険悪なムードになる。
そしてついに我慢が頂点に達する日が来た。その日は朝からおばあさんと、些細なことで言い争いになり、私は悪態をついてしまう。すると「もうアンタ、ここ出てった方がいいわ」と言われ、私も「ああ、出ていきますとも」と言い大晦日の2日前に私とパートナーは仕事と住む場所を失ってしまった。
やるせないムードの中で、オーナーの老夫婦と最後に交わした言葉や彼らの表情がずっと脳裏に焼き付いて、また、彼らに良くしてもらったことなどを思い出し、その度に心が痛んだ。
パートナーは「なんてことをしてくれたんだ…」と、この世の終わりみたいな表情を浮かべおり、毎日のように私を責め、私は自己嫌悪に陥る。
年が明けても全くめでたいムードはなく、こんなに暗い正月は生まれて初めてだった。更に残念なことに年始は観光客が多いせいか、安いバッパーはどこも満員で宿の確保が困難な状況に。
泣きっ面に蜂とはこのことかと思い、私はマッチ売りの少女のような気分になった。しかしそれもこれも私が喧嘩をしてクビになったことに起因するものなので、仕方がない。
結局私達はHobartの市街地から少し遠ざかったキャラバンパークでテントを張って生活することになる。まさにこれぞ私が求めていた冒険サバイバルよ、とやせ我慢で言い聞かせて、自分自身を鼓舞する日々がしばらく続いた。
―パートナーとの別れQueenstownへの旅立ち
テント生活を始めて2、3日経ったある日、パートナーから「もう一緒にはいられない。一人になりたい」と言われる。今度は彼の方がもう我慢の限界で、私に愛想を尽きていたようだ。思えば、WWOOFで共同生活をしている頃から雲行きが怪しくなっており、その頃から徐々に心が離れていくのを感じていたので、寝耳に水というわけではなかったが、それを彼の口から告げられた時はさすがにショックで悲しくてキャンプしているテントの中でオイオイ泣いた。
その翌日、私はまたGumtreeで見つけた1件のローカルカフェのオーナーから連絡がある。私は昨日のしおらしい態度とはうって変って、急に元気でピンピンしていた。空元気だったのかもしれないが、自分でも全く現金なヤツだと思う。元パートナーの彼も「えっ」とあっけにとられている様であったが、これで彼の方も気兼ねなく新しいスタートが切れるので、良いのではなかろうか。
私は電話で軽いインタビューを受け、採用されることになったので、あっさりとその仕事に決めた。場所は西のはずれにあるQueenstownという町だ。 かつては鉱山業で栄えた町だが、今は過去の栄光といった具合で閑散とした場所という噂は聞いたことがあった。
ちなみに電話インタビューの内容は「カフェモカの作り方を述べよ」だったり、追って(私の)顔写真を送ってくれといった要望があったりと少々怪しい。更には後にメールで「寿司は作れるか?」と聞かれたので、これはローカルカフェではなく、イリーガルなジャパレスかチャイニーズカフェじゃないかという疑惑が浮上し、オーナーに直接確かめたところ「ローカルカフェだが、寿司も作って出している」との返答だった。
出発当日、バス停まで見送りに来てくれた元パートナーの彼を見て、「あぁ、これで本当のお別れなんだな」と思うと、今まで彼に迷惑を掛けたことを申し訳なく思い、この時ばかりは本当に寂しくなった。バスに乗り込み、窓の外を見ると、彼も少し泣いていた。
ボーッとした頭と心でバスに揺られること2時間半。Launcestonのバスターミナルに到着する。待ち合わせ場所に現れたオーナーは、十数年前にニュージーランドから移住してきたという50歳ぐらいの男性だった。私達は車に乗り込み、これから何軒か買い出しに行くとのこと、車を走らせた。
最初は自己紹介から始まったのだが、しばらくしてオーナーが「パートナーが1週間前に出て行ってしまったんだ…」とおもむろにカミングアウトしたので、やや重めの恋愛相談ムードに変わり、(私も人のことを言えないが)新年早々やな感じの人に当たっちゃったなぁと思いながら、彼はその後も過去の恋愛遍歴などを語り始める。特に聞きたくもなかったが、仕方なくオッサンの恋愛話に付き合うことになる。
店の買い出しで、何軒も店をハシゴしたり夜の山道を避ける為遠回りをしたりとようやくカフェに辿り着いた時にはもう夜の11時をまわっていた。待ち合わせ時間は昼の1時だったので、10時間以上、彼の買い物ドライブに付き合ったことになる。ちなみに通常寄り道せずに行くと、5時間ほどで到着する距離だ。到着した場所は、何年か昔に古いホテルを買い取ったという2階建てのボロい建物だった。1階には、カフェと最近始めたハードウェアショップ。2階はオーナーとスタッフが寝泊まりしている個室の部屋、リビング、バス・トイレがある。
全体的にあまり手入れがされていないようで、とても衛生的とは言えない雰囲気が漂っている。店がある1階も、通路にはガラクタのようなものがあちこちに無造作に置かれてたりと、すべてが中途半端に仕上がっている状況はますます私を不安にさせた。しかし今はこの状況を分析するよりも一刻も早く休みたかったので、オーナーに案内されたスタッフ用の個室で荷物を降ろして寝る準備に入る。殺風景で不気味な部屋と薄汚れたシーツの組み合わせはリラックスできる環境からは程遠かったが、ひどく疲れていたのですぐに眠りに落ちた。
翌日私の不安はすべて的中し、この胡散臭いカフェの全貌が明らかになる。
まず、ここで働いているスタッフはワーホリの日本人2人。その人達に、「Gumtreeの写真にはローカルっぽい人達が写ってたから、てっきり地元のカフェかと思ってたよ…」と伝えると、「そういえば、オーナーの姪っ子達が遊びに来たときに、何故かコーヒーマシンの前で写真を撮ってた!あれがGumtreeに載せる写真に使われてたとはね〜」という事実を知り呆然となる。なにより一番驚いたのが、勤務時間は朝8時から夕方6時までで、仕事内容はコーヒーを作り、寿司ロールを巻いてピザやパンとケーキまで焼き、無休の上に週$200(宿つき食事無し)という今まで聞いた中で最も不当な労働条件だった。私はGumtreeに載っていた偽の写真に惑わされて勝手にローカルカフェだと勘違いし、ローカルジョブなら最低時給はあるはずという思い込みで、事前に時給を確認してなかったのだ。
自分の不注意でもあるので、完全につめが甘かったとしか言いようがない。それにしても一体、ワーホリはどこまで足元を見られているのだろうか。ちなみに一応セカンドビザのフォームにサインをするというオマケ付きらしく、明らかに不服な労働条件ながらもビザ欲しさにここに来るワーホリが後をたたないのだという。実際に過去に何度か摘発され、政府の監査も入っているらしいが毎回何とかごまかし法の目をくぐり抜けて、現在も生き永らえているといった具合だ。この話を聞き、早くもこのオーナーが信じられなくなった。
私が入った初日の朝から、盛んにカフェに顔を出し、その度に注文をつけてきた。突然、3種類ほどのサンドイッチを至急作れ!と言われる。勝手がわからないので、日本人スタッフも困惑しているようだ。仕方なくサンドイッチを作り始めたところ、10分後に再び現れた彼は今度は「何でマフィンを焼いていないんだ!」と、すごい剣幕で私達を責めたてる。反論する言葉を探しているのか、既に諦めているのか、俯きながらYes,ok okと言い続けている日本人スタッフを見て、いてもたってもいられなくなり、口を挟んで反論した。
「お前はだまっていろ」と言うオーナー。しかし私は食い下がり、同じような内容をもう一度説明したような気がする。その時、彼の怒りが最高潮になっていくのを、その表情から感じた。
その翌日、私はキッチンで朝食のパンを食べていたところ、「話がある」と不意にオーナーが入ってきて、クビを宣告された。クビに至った主な理由は私の勤務態度に問題があるとのこと。具体的には、マフィンについて注意をした時に口を挟んできた、だまれと言ったのにしゃべり続けた。また、日本人2人のスタッフに話しかけて、彼らの仕事をスローダウンしていた、という点があげられた。ペースが落ちたという点については「そんなの初日なんだから説明を受けるために話をするのは当然じゃないか」と反論したが、この虚しい場所からは一刻も早く抜け出したい一心だったので、それ以上戦う気力もなく、言われた通り荷物をまとめて出ていくことにした。が、バスが毎日運行しておらず、悲しくももう1日だけ宿に泊めてもらうことになる。
その1日は何もすることがなく、私はずっと部屋にこもってただ天井を眺めて、ぼんやりと考えていた。古いホテルの跡形だけが残ったさびれた宿。オーナーの趣味だという、奇妙な絵が飾られているリビング。ガラクタに囲まれた古いビリヤード台。お腹をすかせた名前の無い飼い犬。目にするものがすべて侘しいという言葉で集約できた。そんな退廃的なムードの漂う中、夜はオーナーの部屋からビートルズのYesterdayが流れていて余計に悲しくなる。その日はどうやって眠ることができたのか、よく覚えていない。
翌朝、一緒に働いた日本人の女の子が、出発する前に私に手紙をくれた。
わざわざどこかの店で買ってくれたのであろうQueenstownのポストカードの裏にぎっしりとメッセージを書いてくれていて、その気持ちが本当に嬉しかった。その手紙のおかげで、Queenstownでの思い出がすべて悪夢というわけではなくなる。そして私はバスに乗り込み、もう二度と訪れないであろうこの町の、今は枯れ果てた鉱山の風景をバスの中から見送った。
―そうだ、車を買おう
Hobartに戻り、先日泣きの涙で別れたばかりのパートナーとあっけなく再会することになる。
別れてはいるものの、便宜上と言うべきか惰性なのか結局また行動を共にするという微妙な関係になり、今度は車を買おうということになった。できるだけ安い車をとGumtreeで探したところ、Daihatsuのシャレードという車$600(交渉可)が目に飛び込んできた。写真を見たところは、可もなく不可もなくといったところだ。早速車のオーナーとアポを取り、私達はバスに乗ってその場所へと向かった。
オーナーは10代か20代前半のオージーで、どちらかと言うとチンピラ風だ。そして、その若者の父親らしき人物と周りになぜか数人のギャラリーまで連れてきている。車の試乗をさせてもらうと、さびれた車の乗り心地がする。それに、あまり信用できそうにないチンピラオージーから、この車だったら$600ドルでも買いたいとは思えない。「ちょっとこれは…。$400ぐらいならいいんだけどね。」と言うとチンピラ風のオージーは「$500までしか下げれない」と言うので「それなら別の車を探すからいいわ。ありがと」と言って立ち去ろうと歩き出したところ、「じゃあ$450でどうだ!」と後ろから声が聞こえる。元パートナーと顔を見合わせて、まぁ$450ならいいかということになり購入することにした。
チンピラ風オージーがどうも信用できそうない、ということはこの車も信用できるものだろうか…とその他にも突っ込みどころが山ほどあるのだが、とにかく私達はチンピラオージーからそのオンボロの車を購入し、その車で帰路に向かった。
あと少しでバッパーまで着くという時、K&D(大型ホームセンター)の前で車のエンジンはストップし、うんともすんとも言わず動かなくなった。二人とも心配していたことが、いとも簡単に起こってしまった。しかし、冷静に考えてみれば当然の結果と言えよう。いかにも信用できそうもないチンピラからポンコツ車を$450で購入したのだから。
K&Dの入口を塞いでいたので、私達は車を動かす為、前と後ろから必死の形相で車を押す。そういえば日本にいる時、オーストラリアの広大な自然の中で、車が動かなくなりリポビタンDのCMのように仲間と車を押すというサバイバルができたら面白そうだ、などと夢に描いていたことを思い出した。その願望は悪夢という形で現実のものとなり、今私達はHobartの町中にあるK&Dの前で動かなくなった車を必死に押している。
その姿を見た親切な通りがかりの男性が、一緒に車を押してくれた。そして、ジャンプスタートを試みるも車が動き出すことはなく、坂道を利用して何とかパーキングエリアに車を動かし、その日はなす術もなくあきらめることに。あてにしてなかったが、一応先程のチンピラオージーの携帯に電話をするも応答無し。しかし、深夜0時に元パートナーの携帯電話が鳴る。画面を見ると例のチンピラオージーからであった。相当酒に酔った様子である。そしてその数分後、今度は私の携帯にも着信があり、応答するとロレツの回らない状態で何か叫んだり、馬鹿笑いしている。車を売って儲けた金で仲間と呑気に酒を飲んで騒いでいる様子を想像すると、非常にハラが立った。
このチンピラオージーから、その後は非通知で夜中にイタズラ電話がかかってくるという地味な二次災害がしばらくの間つきまとった。私は非通知の着信には対応しないようにしていたが、元パートナーの彼は面白半分に対応していたため、その被害が長引いていたように思う。
翌日、車の状態を検証したところ、どうやら単純にガソリンが切れていたのと(ちなみにメーターが壊れていたのかガソリンの残量が正確ではなかった)、エンジンを何度も吹かした為バッテリーが上がっていたということが判明する。近くの車屋が親切に貸してくれた容器を持ってPetro Stationでガソリンを入れ、修理工の人にバッテリーを充電してもらい、ポンコツ車はまたいつ止まるかもしれない状態ではあるが走りだした。
しかし3日後に元パートナーが空港に知り合いを迎えに行った帰り道で、その車は完全に動かなくなる。
故障の原因はFuelポンプが使い物にならない状態で、レッカー車を呼んで車を撤去する場合、別途$100近くかかるということだ。彼から電話でそのことを聞いた時“故障の為停止中。すぐにレッカーで運びます”というメモを添えて、取りあえず車を置いてくるよう伝えた。メモ書きを残しておけば、チケットを切られることもなくしばらくの間はその場所に置いておける。
夕方ごろ、彼は憔悴しきった顔でバッパーに戻り、私達は対策を練ることになった。とりあえず駄目元だがGumtreeにその車の広告を載せ、故障車(Fuelポンプに問題あり)で売りにかけることにした。そして平行して、Hobart中のディーラー10数件に連絡をして買い取りをお願いするも車種を告げると、「タダで引き取りならできるが…」という店ばかりで私は肩を落とす。また高価買取業者にも連絡を取り、立会で車を見てもらったのだが、同様に「タダで引き取り」という結果だった。
一方Gumtreeは意外にも4人から連絡がある。値段は交渉としていたので、まず最初に連絡をくれたトニーという男性とアポを取った。トニーは穏やかでフレンドリーな60歳ぐらいのオジサンで、車に同乗していた飼い犬のウーフは元気で人懐っこい。趣味なのか本業なのか、自宅でリサイクルをしており、家は部品で埋もれているのだと言う。
トニーの車に乗って、とりあえず故障した車を見に行く。約1週間放置してあったので、車の状態が心配だ。現場に到着すると、車のフロントガラスに張られた紙を発見する。壊れた車を約1週間放置していたためHobartのcity council から赤紙のような通知が車に張られていた。その紙には、『直ちにこの車を撤去すること、そしてこの車の持ち主またはこの車について知っているものは市の監査官に連絡すること』と書かれてある。
何かとんでもないトラブルになってるんじゃないかと思い、気が遠くなり私は今にも泣きそうな状態に。「大丈夫だから、一つずつ解決しよう」と、トニーは私の背中をポンポンと叩いてくれた。そして「私の家でお茶でも飲みながら、状況を整理して話をしよう」と言ってくれたので、私達はトニーのお宅にお邪魔することになった。
トニーの家は聞いていた通り部品で埋もれていた。実験室のような部屋にリビングがあり、机は無いが座り心地の良いソファがあり、そこに腰をおろす。トニーが出してくれた缶のPepciコーラを飲みながら、私達は約1週間前にこの車を買ったこと、その3日後に車が故障したことなど順を追って話した。ゆっくり話していくうちに、私も気持ちが落ち着いていった。
それから3人でService Tasmaniaへ行き、トニーが今回の経緯をすべて説明してくれる。そこで職員に調べてもらい明らかになったことが、所有主はチンピラオージーではなく、全く別の中国人の男性だった。チンピラオージーは車のレジストレーションはおろか、所有主変更の手続きすら行っていなかったようだ。初めから転売目的で中国人からこの車をスクラップ同様の金額で購入したのかもしれない。ややこしい状況の上に、車の故障と放置で事態はよりややこしくなっていたのだ。トニーがいなかったら、私達は途方に暮れるだけでこの状況を把握するまでに、かなりの時間を要したであろう。トニーには本当にいくら感謝しても足りない。その後トニーと一緒にオフィスで所有者変更手続きを済ませた。そして他の業者に頼んでもほぼ無価値のスクラップ同然だったこの車を、$300で買い取ってくれたのだ。
別れ際にトニーは「これからはすべてがうまくいくといいね」と笑顔で励ましてくれた。私達はトニーに表現できる最大限の感謝を伝えて、かたい握手を交わしハグをして別れた。チンピラから買った車は私達の元で廃車となったが、親切なトニーの手に渡り本当に良かった。
人の悪意と善意を一遍に受けたような、1週間であった。
−ジョブハンティング再び
私は大切なことを忘れかけていた。そうだ、仕事を探していたのだった。
私と元パートナーは数日前にGumtreeでLauncestonにあるローカルレストランを見つけ、二人ともレジュメを送り、そしてボスから面接をしたいからという連絡の電話を受けていた。電話口では「いつでもいいからLauncestonに来る時連絡してくれ」と言っていたが、後日こちらから電話を掛けても、メールを送っても応答がない。やはり脈なしか…と思っていたのだが、元パートナーは「取りあえず、レンタカーでも借りて直接レストランに行ってみよう。これは僕の勘だけれど」と言い、最初は納得しなかった私も駄目もとでもHobartを抜け出したいという逸る気持ちで、彼のアイディアに乗っかることにした。私達は早速レンタカーを手配し、翌日Launcestonへと向かう。これで仕事をゲットできれば儲けものだが、収穫無くして帰ることはまた無駄な出費が増えることになる。
そして、この一か八かの賭けは成功だった。
ボスはHobartからはるばる来たことに驚きながらも、とても温かく迎えてくれ私達2人のポジションを確保してくれると言う。そして、この付近に引っ越しをして、落ち着いたらまた再度訪問してくれとのことだった。これで半分決まったようなものだ。確かな希望の光が見た私達の表情は一気に明るくなる。レストランを出て、敷地内の庭で突然寝転がって昼寝をしはじめる彼に、「ここまで来たんだから、ついでにシェアハウスも見ていこうよ」と言うが、面倒臭そうにする彼に「波に乗っている時に失速することなく一気に決めた方が上手くいくんだ」となんとか説得する。私はシドニー時代にシェアハウス探しでつかんだ感覚を思い出していた。
すぐにGumtreeで探してみたが、そのエリアは物件自体、非常に少なかった。値段を考慮の上で辛うじて見つけたのが3軒。うち1軒は電話で話した時に、1年単位の長期契約と言われ諦める。 残りの2軒をアポを取り見に行くことになった。まず1軒目。犬と猫がいるというのは大歓迎だったが、どうも家の中の雰囲気が暗い。あれこれ手が回らなくて中途半端な状態(そのわりに物で溢れている)という環境は、Queenstownのカフェのデジャブを見ているようで、どうしても好きになれず、その場所はやんわりと断ることに。
そして最後に見た1軒は、Launcestonの市街地から仕事場のレストランまでの道のりのちょうど中間地点で車で10分の距離に位置している好条件の、Kings Meadowというサバーブエリアだ。それに家から徒歩5分の場所にColesとWoolworthが道路を挟んで向かい同士に並んでおり、買い物へ行くにも不自由しなさそうだ。
それより何より、とてもフレンドリーで感じが良いシェアメイトのクリスタという女性が気に入った。タスマニア生まれでタスマニア育ちの24歳の彼女は理学療法士として働いており、お年寄りや障害を持つ方のトレーニングをしているという。そして初めて会ったこの日、クリスタは私とお揃いの服を着ていたのだ!これで私がまた勝手に運命めいたものを感じ、彼女を見た時点で私の心はこのシェアハウスに8割方決まっていた。この家で一緒に住んでいるというクリスタの兄は、友達の結婚式の為現在ヨーロッパにおり、来週帰国するそうだ。兄もどんな人だろうと気になったが、クリスタのお兄さんなのだから、絶対良い感じの人に違いない。
家の中を見せてもらうと、日当たりの良いリビングにきちんと整頓された清潔なキッチン。家全体から居心地の良さが伝わってくる。しかも家賃や1部屋$130。私の元パートナーとルームシェアすると、一人当たり$65だ。申し分ない条件の上、一番重要なシェアメイトがとても感じの良い子だったので、即決でこの場所に決めた。この日、仕事にシェアハウスにと大収穫を得た私達は、浮かれた足取りでHobartへと戻った。
さぁ、あとは車だけだ!となった時、またまた嬉しい話が舞い込んでくる。 以前ポンコツ車が高速の下で動かなくなった際に、たまたま横を通りかかり車の状態を見てくれた親切なオージーのオジサンが連絡をくれたのだ。
彼は$1800で売りたい車があるのだが、「君たちは不運に見舞われているから」と言い不憫に思ってくれたのか、その車を$1300で売ってくれるらしい。聞けば96年のTOYOTAカムリのステーションワゴンでコンディション良好とのこと。早速翌日にアポを取り、実際の車を見せてもらうことになった。
トランクのドア壊れているのと、ガソリン注入口の扉が外れてなくなっているぐらいで、ボディは傷一つなく、大切にされていたことが伺える。試乗されてもらうと、私達が以前$450で購入した車とは比べ物にならないくらい安心感があった。さてここから、値段の交渉に移る。元パートナーの彼はこういった交渉ごとにはめっぽう弱く、私がいつも交渉人となっていた。私も別に交渉が得意なわけでも好きでもなく、たいした理論武装もなかったが、えいやーの精神論だけで突っ走っていたように思う。
この時、残高は確認していなかったが、随分と私の持ち金が少なくなっており確実に$300は切っていた。そのため、まとまったお金ができるまで、まずは元パートナーの彼が払ってくれることになったので、私にできるのは少しでも値切って負担を減らすということであった。この車を善意で安く売ってくれようとしているのに、その善意に更に便乗して値切るなんて、なんて自分は卑しい人間だと思っていたが、今の生活とこれからの仕事がかかっている。そうしてオーナーの男性と話をし最終的に$1100で手を打ってくれた。
晴れて壊れていない車をゲットした私達は、荷物をまとめてバッパーを後にし、早速シェアハウスに移動する。 ボスにも連絡を取り、新しい生活の準備は万端に整った。ただ、果たしてこれは私と元パートナー双方が望んでいたことだろうか、良いのか悪いのか、数々の疑問が残るまま、また第二の共同生活へとなだれ込む恰好になる。
ここで私の懐事情だが、タスマニアに来てからこの1か月半、職が見つかり移動してはクビになるを繰り返していた為、交通費や車の修理費、宿代などで出費がかさみ、気づくと私の銀行口座の残高は$8になっていた。少なくても$200ぐらいはあるであろうと思っていたので、ATMの画面に表示された$8の数字を見た時は目を疑った。
それでも家の付近に住みつく野良猫のエサを買ったりして、元パートナーからは「お前はバカだ」と言われ非難を浴びたが、当事者本人の私は呑気にやっていたのだと思う。翌週からは晴れてローカルレストランで働くことが決まっていたので、今週いっぱい$8で生き延びればよいだけと思うと、さほど不安にはならなかった。
―理想の生活ってなんだろう。自己完結するということ。
シェアハウスに移り住んでしばらくした時、クリスタの兄、リンダンがヨーロッパから帰国した。家の近所にある4WD専用の修理工として働いているというリンダンは思っていた通り、明るく話好きでとても感じの良い人だった。そして待ちに待った仕事は、ヴィンヤードに囲まれたローカルのレストランで季節の良い夏にかけては毎週末結婚式があり、100人を超える団体の予約が入っている。タスマニアのパンフレットや情報誌には必ずといっていいほど載っている、地元の人なら言わずと知れず有名店らしい。これぞ夢にまで見ていたローカルジョブ!今までの苦労が報われたことを嬉しく感じる。ワーホリ10か月目にようやくゲットしたローカルジョブ。オーストラリアへ来て1ヶ月後にとったTFN(タックスファイルナンバー)に今ようやく出番が訪れるという。
私と元パートナーを除き、スタッフ全員がオージー(うち1人は永住権を取得したフランス人)である環境も初めての体験で新鮮だ。私達は二人ともキッチンで働くことになり、仕事内容は皿洗いの他にハーブの葉をちぎったり、野菜を切ったりといった内容だった。
そして、この仕事で私を大きく変えてくれたのは、Kitchen Handの達人マークとの出会いだ。彼は作業が早いことはもちろんのこと、仕事全体がオーガナイズされており、動きに全く無駄が無い。有能だからといって威張るわけでも、あれこれ注意することなく、私が分からないことがあると丁寧に教えてくれる。寡黙なマークの仕事に対する姿勢を見ているだけで刺激を受け、毎回新しい発見をしては感動を覚えていた。オーストラリアに来て初めて仕事のロールモデルのような人ができて、私は今までになく、自分の動きが俊敏になっていくのを感じだ。
仕事でやりがいを感じることが多くなるが、家に帰ってふと今の状況を考えると手放しでは喜べない自分もいた。同じシェアハウスの同じ部屋で暮らし、同じ仕事場へと出かけていく、元カップルの私達。あぁ、物理的な距離が近いもの同士の心がこれほどまでに別離していることの辛さよ、といった具合である。
田村さんから頂いた“グレーの色合いというか、グラデーションみたいな変化、墨絵のような「枯れた味わい」とかを賞味するのが大人だよ”というアドバイスを励みに、この曖昧な状況を受け止めて、判断せず流していく、そしてその向こう側が見てみたい。そんな中でも幸せはいくつでも見つけられるということを、自分の中で実証してみようと思った。思いつく限り、やりたいことをやろう。
まず初めに、何か新しいことにチャレンジしたいと思い、日本語教師が頭に浮かぶ。早速Gumtreeで“日本語教えます”という広告を出したところ、1人から連絡があった。本当に手探りの状態で、2回限りのレッスンではあったが、初めて人に教えることができた良い経験になる。
ある時、Launcestonにある教会で、瞑想と説法のクラスがあるという情報を入手し、面白そうだなと思い、参加することにした。そのお坊さんはイギリス人の若い男性で、訛りのない英語が聞きやすい。また身近な例での話が多かったり、話の内容も面白く、1時間半の説法はあっと言う間だった。
「幸せが訪れ、すべてが変わるという興奮の先には、失望や喪失感が伴う。興奮と幸福を混同させてはいけない」この言葉を聞いた時、オーストラリアに来れば、幸せになれるんじゃないかと考えていた過去の自分を思い出す。そしてお坊さんは続けて「本当の幸せとは常に無害である。害を伴うような一過性の幸せで自分自身を誤魔化してはいけない」と言い、その言葉がしばらく胸の中に響いていた。
また、「この社会でどうやったらお金儲けができるかを考えるのと同じ様に、人々はどうやったら自分の投稿に対して、他者からいかに多くの“いいね”が得られるかを考える。SNSは日々の空白を埋め、社会の中で感じる疎外感から解放されるためのツールなのだ。“いいね”ボタンはその通貨のような役割なのだろう」と。便利さを否定はしないものの、その侘しさは文化や宗教に限らず共通に感じているものなのかもしれない。参加者たちはこの時、皆深く頷いていた。
またある時は、なぜだが無性に折り紙が欲しくなり、私はわざわざE-bayで注文した。そして暇さえあれば折り紙を折り、完成した作品をリビングに飾ったり、近所の老人ホームに寄付したりしていた。
仕事を始めて1ヶ月半が経ったある日、翌週のシフト表を見て唖然とする。今まで週5日(忙しい時は週6日)入っていたシフトが週2日になっていたのだ。 ちなみに元パートナーの彼は、ちゃんと週5日入っている。
突然の戦力外通告を受けた気分になり、私は激しく落ち込む。そのシフト表を見た時、その場にボスはいなかったので、他に誰にも言えずしょんぼりして帰ったのを覚えている。その後も変なプライドが邪魔をして、結局直接そのことをボスに直接話すことはできず、悶々とした日々を送る。今まで働いた場所はクビになる理由も しかしどう考えても最もらしい理由は見当たらない。唯一挙げるとすれば、元パートナーと仕事のやり方を巡って軽い口論になり私は一時的に機嫌が悪くなったという日が一日あったこと、そして元パートナーの彼はボスにたいそう気に入られている、という点ぐらいであった。
ここでまた発想の転換が必要な時がきた。それを促してくれたのが、本屋で偶然手にした“The MAGIC”という一冊の本だった。凝った文法的表現もないため、読みやすい。要約してしまうと、“小さなことに感謝すること、幸せの数を数える”といったシンプルな内容なのだが、嫌なことや不安・寂しさなどでがんじがらめになっていた自分の心が、感謝という幸せに目を向けることによって、気持ちがずっと楽になることに気付く。無理やり正当化しようとか、ポジティブに考えなくては、と思うと辛いのだが、視点をずらして考えると物事は案外スムーズに進むものだ。その本によって、タイトルの如く何かが魔法の様に劇的に変わるわけではなかったが、自分の気持ちが整理できたことが一番の効果である。目の前の状況に嘆くより、なるべくシンプルに考えるように心掛けた。
元パートナーの彼の誕生日にはサプライズで寿司と天ぷらを作り、ケーキも焼いた。天ぷらを揚げる際に換気を忘れていたため、けたたましい音で火災報知器が鳴り、アラーム解除の仕方が分からず、しばらく鳴り続ける。慌てて換気扇を回し窓を開けると、近所の人が心配して外まで出てきていた。
誕生日のサプライズは喜んでもらえてよかったのだが、翌日油が減っていることに文句を言われ(調味料はシェアしていた)また喧嘩が勃発し、心底情けない気分になる。むしゃくしゃする気持ちを抑えて、私はまた部屋の片隅で折り紙を折っていた。オーストラリアくんだりまで来て、折り紙を折っている自分が不思議でしょうがない。なんとも滑稽な状況に笑えてきた。心のどこかで、何かが変わる期待をしていたのだけれど、そのうちに結局これは袋小路を先延ばしにしている状態に過ぎないということに気付く。そんな時、ある言葉を目にした。
If you could love the wrong person, imagine how much you could love the right person.
シドニー時代のシェアメイト、アナンタがFacebookの近況に載せていた言葉だ。これを見た時、もうそろそろ潮時かな、と感じた。私が望んでいた結果にはならなかったが、デッドエンドを見て納得している自分もいる。腹を括って出発する時が来たのだ。あぁ今度こそ、本当のお別れなのだと。レストランのシフトも日に日に減っており、多い時で週3日、少ない時は週1日ということもあった。 このレストランから、元パートナーから、そしてタスマニアという土地から今やっと納得して離れていくという、自分の気持ちを感じ取る。
それから私は日本帰国への準備を進めた。
今日でレストランの仕事も最後かぁと感慨にふけっていた当日の朝にボスからメールが来て、「予約が減ったから」と私のシフトがあっけなくキャンセルされる。しかし最後の挨拶をしたくてレストランを訪れたところ、日曜日でいつも以上に大忙しでてんやわんやな状態だった。結局最後の最後まで、私はこのボスが解せなかったが、それ以上は追及しないことにした。それにこのボスが私達を受け入れてくれたからこそ、ここで働かせもらえたということの感謝はいつまでも忘れずにいようと思う。
シェアハウスを出て空港へ向かう日、元パートナーの彼に対する感謝の想いを手紙に綴り、枕もとに置く。空港に見送りに来てくれた彼をゲートをくぐる前、振り返り見たら鼻の先が赤くなっていたので、もしかしたら少し泣いていたのかもしれない。ちなみに私の手紙はあろうことにしばらくの間気づかれることなく、数日後というマヌケなタイミングで発見され、彼から「なんか手紙が出てきて読んだぞー」という連絡を受け脱力した。
◆シドニー再び
―カウンセリングとパラレルワールド
10ヶ月ぶりにシドニーを訪れた私は、かねてから希望していた、田村さんの奥様のカウンセリング(キネシオロジー)を受ける。オーストラリアで起こった数々の出来事、その時の自分の気持ちや行動を点で結んでつなげて整頓してみることに興味があったのだ。また、何度も理性を失い、自分が分からなくなっていたことも、あれはなんだったのだろうと思っていたので、カウンセラーの方の客観的な意見を頂きたかった。カウンセリングの中で、「中庸を知るには、両側に大きく振れる経験が必要」と言われた時に気付く。今まで日本にいた私は、ここまで大きく振れるという経験がなかったことに。それを実現させてくれたのが、このオーストラリアだ。精神的な試練の数々に本当に辛い日々もあったが、ある意味自由に暴れまわったとも言える。
また、「瞬発的にこらえることと、爆発することは本質的に同じである。なぜなら、そこに自分の意思という選択肢が介入していないから。」という言葉にも気づきがあった。最後にタスマニアで決断した、結果的には爆発することなく、納得した上でタスマニアを離れることにしたあの決断は正しかったのだと思えた。そして納得とは、頭にある“気”が胸のあたりに下がってきてしっかり受け止めた、腑に落ちた状態であること。この気持ちを、どんな時も覚えていようと思った。
同じシドニーの街に、CentralやTown Hallの駅に10ヶ月前とは全く別の気持ちで立っている。自分自身であることには間違いないのだけれど、何だかパラレルワールドにいるような感覚だった。
そして、かつてELSISで出会ったクラスメイト達に会う。懐かしいような新しいような、その再会が純粋にとても嬉しかった。そして、私は彼らに以前より素直に自分を自分の言葉で話せていることに気付く。この時に本当にコミュニケーションがとれたのだ。これは英語力が上がったからではなく、自分が素直になれたからだと思う。彼らは口々に、「教室の片隅にひっそりと座っていた優等生が、こんなに生き生きとした姿になって!」と言い、心底驚いている様子であった。そして、その日の帰りにクラスメイトのチェコ人のうちの一人から、二人きりになった時に突然の告白を受け、私はひっくり返りそうになる。
しかしそれは普遍的ではなく、流動的で刹那的なもので、そこ居合わせた者と内容で偶然起こった化学反応のようなものだった。「このことが私の人生において何を意味しているのか…」などと妙に深く考えずに、ただ受け止めて流す出来事というのが人生には往々にして訪れるということを知る。
また、今回の件で、旅は最後まで何が起こるか分からないから気が抜けないなぁと感じた。そして、誰かにとって相対的な存在ではなく、自分自身にとって絶対的な存在になりたい、などという今後の抱負と複雑な思いを抱えながらシドニーを出発し、ケアンズへ向かった。
ケアンズでは熱帯雨林をトレッキングしたり、グレートバリアリーフでシュノーケリングとダイビングを体験してテンションが上がる。ケアンズには、良くも悪くも観光慣れした土地独特の雰囲気があり、それはそれで楽しいなと感じた。後先のことを考えることなく純粋にオーストラリアを楽しんだ4日間だったように思う。
すっかり日焼けした私はバッパーでシンガポール人と間違われ、なぜか満足した気分で日本行きの飛行機に乗るため空港へと向かった。
◆旅の終わりに思うこと
当初の目標、田村さんに出された課題が「なんでも優等生的に小さくまとまら ないで、ある程度ゆとりもって流していく度量をつけること」だった。
結果、優等生もなにも、かなり醜い姿で取り乱し、自分を失うことによって自己実現を図るという模索の日々だったように思う。
無数に存在する“幸せの形”をオーストラリアで見ることで、白黒つけないという選択を知った。思えば私は、何事も二元論で片付けようとしていた。良いか悪いか、白か黒か。そのため自分の可能性も広がらず、二次元的な構造になっていたのだと思う。悩んで考えこむわりには思考範囲が狭く、常に二者択一の極論にワープする。そして、基本的にあらゆるものごとから逃げていた。
何かがありそうな気がする。ここを出れば私は変われそうな気がする。
しかし、逃げたところで辿り着いた先は、見たくなかった自分をみつめること、自分自身を知ることであった。
いわゆる“オーストラリアで自分探しの旅”で私は自分を失い、そして長い間縛られてきた、世間がこしらえた幸せの金型をはずし、リセットできたからこそ気づけたのだろう。時にヒステリーになってワインの瓶を投げ、時に理性を失いオーナーと喧嘩 して首になる。そして大切なことは目の前におなかをすかしているネコがいれば餌をあげることであり、この矛盾したすべてをまとめて“自分”なんだということが分かる。この時、煮詰まっていた私の脳みそに、新たな思考回路が開通したのは確かだ。
そんな気づきを得て日本に帰国して、友達にオーストラリアはどうだったかと聞かれると、前述の内容をすべて説明する訳にもいかず「ジンベイザメと泳いだり、エビ釣り漁船の乗ったものの船酔いが酷くてリタイアし、ファームでは仕事が遅くてクビになり、太っちょのカンボジア人と呼ばれたり、基本的にそこら中で喧嘩をして仕事をクビになった」という稚拙な表現になってしまい、「あんた一体オーストラリアに何しにいったの」と呆れ顔で言われる今日この頃だが、私はこの旅の展開を結構気に入っている。
完
補充質問
成田さんの後半の胸突き八丁みたいな部分は、かなり壮絶な戦いになってると思います。自分にこれだけ向き合えるというのは、なかかな出来そうで出来ないです。「自分が自分であること」を自分で叩き壊していくわけですから、自分で腹開いて手術するような、かなりしんどい作業です。
で、問題は、「なんでそこまで出来たのか?」です。
つまり「やらねばならない!」というモチベーションが切羽詰まった感じであったと思うのですね。本来の自分とよそ行きの自分が乖離しているけど、「本来の自分が出てこれなくなっちゃった病」みたいな、それを直したいという根源的な欲求。やっぱそれは強かったのでしょうかね?
そして、お医者がよく言う「どうしてこんなになるまでほっておいたのですか?」であり、「自覚症状はなかったのですか?」です。なんか違うなあって妙なズレ感というのは、いつ頃から感じていたのでしょう?おそらく無意識的にはブランキーに出会って、それに心惹かれた時点では出てたと思うのですが、それ以前、例えば小学生とかその頃から「なんか違う」感はあったのでしょうか?
そして「違う」感が芽生えてからの後の展開ですけど、すくすくと進学して、就職もして、アメリカ留学もして、それなりに自由になるお金もあって豊かなOL消費生活を満喫して、、って、よそ行き人格もどんどん出世していきますよね。イケてます。この進展によって「別にこれでいいじゃん、正解じゃん」的にズレ違和感は後退したのか、それともそれとは関係なく一貫してズレ感覚はあったのか、また強大になっていったのか?です
あと、素朴な質問ですけど、デトックスが済んで、長年のズレが収まっていっている今日このごろですが、「今のお気持ちは?」です。自分が自分であることに「しっくりきている」「腑に落ちてる」という感じじゃないかなと思うのですが、ものすごい主観的で、生理的で、皮膚感覚な表現でいうと、「どんな感じ」ですか。別にベンジーのように「メロンソーダとチリドックがあれば生きていける感じ」とか、すごいのでなくてもいいですけど(それでもいいですけど)、自分の一番しっくりくる言葉で表現すると、どんな感じでしょうか?
どちらも個人的に聞いてみたいです。
田村さん
こんにちは、成田です。
返信遅くなってしまって、申し訳ありません。。。! ダーウィン入りしてから国立公園を回って(といってもまだ2か所だけど)、キャンプしたり、クロコダイル見たり早速遊びから入ってました。写真はカカドゥ国立公園のひとコマです。
カカドゥから帰ってきた翌日にジョブインタビューがあり、無事仕事ゲットし、シティホテルのハウスキーピングをしています。ちなみに、ダーウィンってオーストラリアで最も賃金が高い場所なんですね。事前情報無しにいって、びっくりしています。今の仕事、時給平日は23ドル、日曜日は32ドル、祝日は50ドル(@@)です。お金じゃないよ〜と思ってますが、次に待ち受けるアドベンチャーのためにお金を使いたいので、稼げる時に稼いでおこうという感じです。
ダーウィン入りする前にマレーシアで遊んで、ダーウィン着いてからも遊んでたので、またもや銀行口座が本格的にゼロになりました。一遍ゼロになると色々リセットできて、良いですね。 今回の仕事もそんな矢先に舞い込んできたチャンスだったので、最初に遊んでおいて良かったと思ってます。
今はシェアハウスをのんびり探しながら、バッパー生活を満喫しています。バッパーでの出会いが面白くて、バッパーで暮らすために仕事してるようなものかも。笑
マレーシアは初めて行った国なのに親しみを感じ、何やら懐かしさのようなものまで覚えた不思議な国でした。屋台のオッチャンとかオバチャンの働いている人達に一人一人に顔がある、というか。働いている姿が生活感丸出しで、それがすごく人間味があって好きになりました。
町の人々は、独自の強いアクセントで何食わぬ顔で英語を話していて、それが彼らのアイデンティティのようで、何だか羨ましくって。西洋人のように英語を話そうとしていた自分がいかに胡散臭くて、ダサく思えてきました。笑
彼らは自分の本来の性格の上に、英語をしゃべっている感覚で。
きっとそれが当たり前かもしれないんですけど、
私の場合は日本語をしゃべっている自分(優等生)とは別人格で、英語をしゃべっている自分(西洋人っぽく振る舞おうとする自分)がいて。だから本からの引用や、他の誰かからの借り物の表現だったら、今持っている基本的な英語力を駆使してそれなりに使えるんですけどそれじゃあやっぱり自分の表現能力には限界があるし、何より本来の自分と直結していないから、どんな美辞麗句な英語を並べても、誰にも何にも響かないという。。
「英語をしゃべる自分」という別の人格がこしらえられていた。ここをクリアする時なのかもしれません。
私は一体どれだけ別の人格を作りたがるんでしょうかね、まったく。
ひょいと立ち寄ったマレーシアという地で、オーストラリアワーホリ2年目の課題が見つかるとは、思ってもみませんでした。そして旅を重ねる度に、よそ行きの自分の価値がどんどん失われていきますね。
すみません、前置きが長くなってしまいましたが、
お忙しい中、体験談を添削して頂きありがとうございます!
過去のメール、喧嘩の内容まで書いてあって後から読み返すと、お恥ずかしい限りです。これ、全部載せられるんでしょうか?!^^;でも客観的に読んでもらった時に、メールの方が臨場感(?)が出るようでしたらその方が光栄なんですけど、改めて見て「う、うわぁ・・・」となってます。ハハハ。
さてさて、補足質問についてです。
>成田さんの後半の胸突き八丁みたいな部分は、かなり壮絶な戦いになってると思います。自分にこれだけ向き合えるというのは、なかかな出来そうで出来ないです。「自分が自分であること」を自分で叩き壊していくわけですから、自分で腹開いて手術するような、かなりしんどい作業です。
で、問題はなんでそこまで出来たのかです。つまり、やらねばならない!というモチベーションが切羽詰まった感じであったと思うのですね。本来の自分と、よそ行きの自分が乖離しているけど、本来の自分が出てこれなくなっちゃった病みたいな、それを直したいという根源的な欲求。やっぱそれは強かったのでしょうかね?
基本的に楽しくなくなっちゃったんです。借り物の自分に嫌気が差していました。
大袈裟かもしれませんが、このままいくとそのうち自分が崩壊すると思いました。
漠然と、でもはっきりとそう感じたので、それに気づいたからには、パンドラの箱を開けてしまったというか、もう後には引けないなぁという感じです。
オーストラリアに来たのもそのための冒険で、でもやっぱり前半戦は取り繕っていて素直になれない自分がいました。
シドニー時代は本来の自分が顔を出しては引っ込んだり、うまく自分自身を掴めずにいました。
そして中盤の、森の中のアートギャラリーでのウーフ体験あたりから、自我というかエゴみたいなのがとめどなく流れ出てきて、手におえない状態になり(笑)もうこれと向き合わずはおれない状況でした。
>そして、お医者がよく言う「どうしてこんなになるまでほっておいたのですか?」であり、「自覚症状はなかったのですか?」です。なんか違うなあって妙なズレ感というのは、いつ頃から感じていたのでしょう? おそらく無意識的にはブランキーに出会って、それに心惹かれた時点では出てたと思うのですが、それ以前、例えば小学生とかその頃から「なんか違う」感はあったのでしょうか?
小学生の頃は、逆に自分の人格を消すことに必死でした。転勤族だったので、小学校を3回変わり、転校生っていうだけで最初ばかりは好奇の目にさらされて。もともと内弁慶の恥ずかしがり屋であがり症だったので、変に目立つことは苦痛以外の何でもありませんでした。
きっとその弱点を克服し、転校する度に新しい自分デビュー、とかできたら面白かったんですけど、私の場合は、ただ目立たぬよう、目立たぬよう生きたいと思っていました。転校生というのを強く意識し過ぎていたせいか、人と同じが良いと思い、無難・安泰を求めて小学生ながら八方美人に振る舞っていたように思います。
きっとこの頃から既に、本来の自分が楽しいかどうかよりも、自分がきちんと規定値に入っているか、それが基準になっていたのかもしれません。
それが思春期を迎えた中学生になると、また違ってきました。
自分って何?という漠然としたテーマにぶちあたります。哲学的に考えるような思考能力は持ち合わせてませんでしたが、きっと思春期の誰しもが通過する自我形成の中で、小学校生活とは一変して”人とは違う”を求めるようになり、ブランキーの音楽に出会ったのが15歳でちょうどこの頃でした。
高校でも思うがままに行動してました。とはいうものの、一応ちゃっかり進学校に入学していたので、その中で”人と違う”をテーマに突っ走っていた私は結構浮いた存在だったと思います。
しかし受験を控えた高校3年生の春、『規定値に入らなければいけない』という暗黙の掟が再び私の元に忍び寄ります。一旦そのスイッチが入ると、まっしぐらに優等生モードに切り替わり、突如大学受験へと進路を変更しました。
もともと、専門学校に行きたいと漠然と考えていたので、周りの友人達が私が大学受験に向けて猛勉強を始めた様子を見て、逆に心配していたのを覚えています。
こうやって中高を振り返ると、あっち行ったり、こっち行ったり散らかり放題やって、あとはちゃっかり優等生コースというパターンを踏襲してますね。
>「違う」感が芽生えてからの後の展開ですけど、すくす くと進学して、就職もして、アメリカ留学もして、それなりに自由になるお金もあって豊かなOL消費生活を満喫して、、って、よそ行き人格もどんどん出世していきますよね。イケてます。この進展によって、「別にこれでいいじゃん、正解じゃん」的にズレ違和感は後退したのか、それともそれとは関係なく一貫してズレ感覚はあったのか、また強大になっていったのか?です
一時的には後退しました。大学は第一結局希望は叶わなかったのですが、唯一1大学だけ、英語科を受験していて、そこに受かったので「英語かぁ〜まぁいいか」と思いそのまま進学します。その学部はその年に設立したばかりだったので、ちょっと面白そうかなとか思いながら。
大学在学中に経験したアメリカへの交換留学は、やりたい放題やって、アメリカナイズされたり若気の至り満載でしたが、思う存分楽しんだ記憶があります。日本では考えられないようなハプニングが毎日のように起こるので、最初の海外生活ということもあってか、かなり刺激を受けました。 そして、社会における許容範囲というのは案外幅広いものなんだ、と感じ(あくまでアメリカ基準において)この時ばかりは私も自由になれたような気がします。
しかし、大学4年生で帰国した時には、周囲は就職活動真っ盛り。 遅れをとっていた私は、慌ててリクルートスーツを買い揃え、皆にならって就活を始めました。ここでまたふと気づいたんですが、要は単純に周りに流されやすいんですよね(^^;)
私がエントリーした会社は、留学経験が多少のアドバンテージになる企業だったので、難なく就職することができました。就職して1〜2年は楽しかったです。ボンヤリと夢に描いていた、『英語を使って海外とやり取りをする仕事』が叶ったので。
しかし、3年目で初めて一人暮らしを始めた頃から少しずつ変わってきたように思います。自分と一対一の時間が一気に増えるので、否がおうにも自分と向き合わずにはいられないという。
そしてある時、自分の夢だと思っていた仕事が、実は世間がこしらえた、留学後の大学生が就職する先で好ましいとされる仕事で世間がこしらえた自分の夢であることに気づきました。
最初は「なんかイイじゃん」、と思っていたのが、「いや、ちょっと待てよこれで本当に良いのか?」という心の声が聞こえるようになり、いつの日からか「いや、これで良い訳がない!」となりました。
それからはもう、自分探しに明け暮れる毎日です。まず、どこでどうなったのか経緯は忘れましたがマクロビオティックに没頭し、食に対してストイックになったり、スピリチュアルカウンセラーに名古屋から奈良までわざわざ何度か通ったりもしました。周りからも「大丈夫か?」と心配される始末。とりあえず、本物っぽいものを見つけては手当たり次第に実行する毎日でした。
かくして数年が経ち、ふとしたきっかけで、またブランキーの音楽を聴くようになります。 そして漠然と「なんだかよく分からないけれど、そろそろ野生にもどる時が来た」と思いました。
>あと、素朴な質問ですけど、デトックスが済んで、長年のズレが収まっていっている今日このごろですが、「今のお気持ちは?」です。自分が自分であることに「しっくりきている」「腑に落ちてる」という感じじゃないかなと思うのですが、ものすごい主観的で、生理的で、皮膚感覚な表現でいうと、「ど んな感じ」ですか。別にベンジーのように「メロンソーダとチリドックがあれば生きていける感じ」とか、すごいのでなくてもいいですけど(それでもいいですけど)、自分の一番しっくりくる言葉で表現すると、どんな感じでしょうか?
単純に楽しいなぁ〜と思う時間が増えました。笑っていたら、あぁなんだか幸せという気分です。
オーストラリアに来て”本当の自分を知った”、というよりかは、”本当の自分に素直になれるようになった”という感じです。
それに素直になると、人と自分の違いなんてどうでもよくなってきて、むしろ思った以上に共通点が多かったり、人との出会いが豊かで面白いものであることを本当の意味で知った気がします。
ただ、腹解体作業を行っても、見えたのは氷山の一角のようであり、また実体の無いものなので(ただそれを感じられたというのは、私の中で大きかった)、まだこれから旅は続くんだなぁと。
どれだけ自分が持っているものを人に与えられるか、そして人の懐に入っていくこと。オーストラリアでは(というか世界共通か)この2つが本当に大切で、英語のスキルではないんだなぁと実感する毎日です。
という訳で、まだまだオーストラリアには勉強させてもらってます!
★→体験談の成田真衣子さんの紹介文に戻る
★→留学・ワーホリ体験談の目次に戻る
★→語学学校研究へ行く
★→ワーホリの部屋に行く
★→一括パック現地サポートを見てみる
★→APLaCのトップに戻る