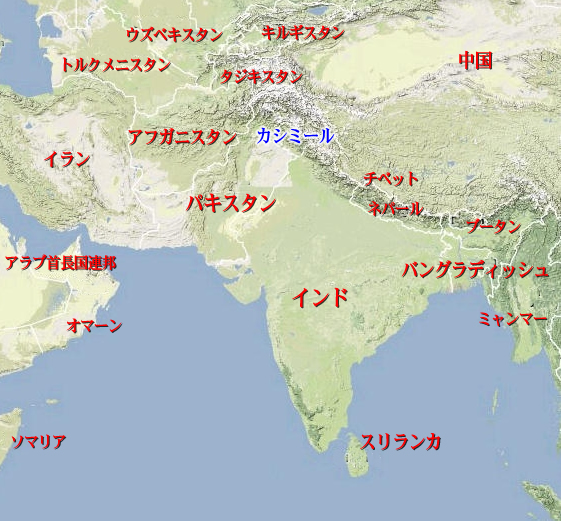パキスタンの独立・建国記念日はインドと同じ、1947年8月15日。覚えやすい日で、日本の終戦の日から丁度2年後です。
インド編の復習ですが、イギリス植民地時代はパキスタンもインドもバングラディシュもひっくるめて「インド」だったのですが、イギリスから独立するにあたって、イスラム教徒とヒンドゥー教徒との対立が起き、イスラム教徒はパキスタンというインドとは別路線でいくことになりました。パキスタンが今の位置になったのは、もともとイスラム教徒が多く住むエリアだったからです。同じ理由でバングラディッシュもパキスタンの一部(東パキスタンとして
)独立しています。
といっても、あるエリアが一人残らずイスラム教徒で、その他のエリアにはイスラム教徒が一人もいない、、なんてことはなく、インド全土で民族大移動のような引越騒ぎになります。また、全てのムスリムがパキスタンに引っ越したわけでもなく、今なおインドの人口の10%以上はムスリムです。

パキスタン建国の父と呼ばれているのが、
ムハンマド・アリー・ジンナーという人です。この人の誕生日は今でもパキスタンの国民の祝日になっています。ガンジーやネルー、チャンドラボースがそうだったように、ジンナーもイギリス帰りのインテリで
あり、19歳で弁護士になるという当時の最年少記録を持っています。
著作権の終了した画像があったので貼っておきますが、中々シャープな顔立ちで男前ですが、どこかしら俳優のケビン・ベーコンに似てると思うのは私だけでしょうか。
インドに帰国したジンナーは弁護士事務所を成功させつつ、政治活動に入り、国民会議派のメンバーになります。1896年、ジンナーはまだ20歳です。40歳になる頃には全インドムスリム連盟の代表に選ばれ、国民会議派とともにイギリスに対して、インドの自治権を要求します。この頃、南アフリカからガンジーがインドに帰国します。ガンジーの運動は、一言でいえば「ふつーのインド人」を全面に押し出したもので、ガンジー自身、洋服も着ず、英語も喋らず、ヒンドゥーの教義に忠実でありました。
しかし、「ふつーのインド人」として普遍的なものを求めるガンジーのあり方は、大多数のインド人に浸透していきますが、同時に「ふつーでないインド人」の反発をも受けます。これまでの独立運動を指揮してきた国内のエリート層、あるいは最下層のインド人、さらにはヒンドゥー教ではないムスリムに警戒心を起こします。ガンジー自身はよく多くの人達のとともにというつもりであろうし、ヒンドゥー教だけをことさらにプッシュするつもりもなかったのですが、広く大衆へという最大公約数的な呼びかけが、そこに入りきらない人々からは嫌われてしまうという。ここが難しいところですが、ある程度大衆運動として盛り上げる必要はあるけど、かといってあらゆる少数派も含めていくと散漫でまとまりがなくなるうえ、メッセージ性も無くなるという。
ジンナーは、社会上層エリートとして穏健の改革を望んでいましたし、ややもすると危険な大衆運動を警戒していました。また、ヒンドゥーという宗教的色を出すと、ムスリムに対する要らぬ反発感情を巻き起し、インドを割ってしまうという懸念もありました。結局、後年においてジンナーの懸念は当たってしまうわけですが。1920年、ジンナーは国民会議派を離脱し、ガンジーらと距離を置きます。といっても敵対関係に入ったわけではなく、ムスリムとヒンドゥーの交渉や調整に腐心します。
1928年、国民会議派を指導していたネルーは、インドの即時独立を訴えると共に、これまでの約束であったムスリムの分離選挙が実行不可能である旨表明します。これでまた一悶着起きるのですが、この問題の背景には、単純に数の論理でいけば過半数を占めるヒンドゥー勢力の独裁状態になってしまうから、少数派であるムスリムには特別枠を設けてバランスを取らねばならないという発想があったからです。そのため議会の3分の1をムスリム議員に当てる等の案が議論されていました。しかし、人口比を越えてムスリムを優遇するのは不平等だと感じる人もいるし、広大雑多なインドを一つの国家としてまとめ上げていく立ち上げ期には強力の中央政府が必要だというもっともな意見もありました。しかし、インドを一つにまとめていけばいくほど、少数派ムスリムは貧乏くじを引かされかねないわけで、そこでギリギリの折衝が行われます。29年、ジンナーはジンナーの14条と呼ばれる対案を出しましたが、国民会議派や他の勢力から認められませんでした。
苦悩するジンナーですが、この時期、泣きっ面に蜂のように奥さんと離婚します。奥さんであるマリアムとは、1918年にゾロアスター教という宗派の違い、24歳も年下、しかもジンナーは二度目の結婚という何重もの壁を乗り越える大恋愛の末結婚したのですが、ジンナー多忙のゆえに夫婦関係がおかしくなってしまったらしいです。欧州旅行などをして修復をはかったものの空しく、27年に離婚、さらに29年には奥さんが病死してしまい、ジンナーは公私ともにドツボ状態に陥ります。
一方、独立運動の方はなかなか進捗しません。1931年、イギリスが茶番のような一時逃れのロンドン円卓会議を開催したのですが、出席したジンナーは「あ、こいつら本気で独立を認めるつもりはないな」と茶番性をすぐに見抜きます。何かもがイヤになってしまったのでしょうか、ジンナーはイギリスの法曹界に戻ってしまいます。「もう、俺、知らんもんね」くらいの感じだったのでしょう。
しかし、ジンナー以上の人材のいないインドのムスリム連盟から懇願され、3年後にジンナーは再びインドに帰り、ムスリム連盟のてこ入れを始めます。しかし、ジンナーの予感(将来的に独立インド内ではムスリムは少数派として押しのけられてしまう)は、早すぎたのか、まだ一般民衆にまでは浸透しておらず、選挙でボロ負けするなど、活動は壁にブチ当たります。とは言いながらも、インド内部での大衆運動=ヒンドゥーの盛り上がりが鏡のようにムスリム社会に反映され、将来に漠たる不安を覚えるムスリム民衆も増えてきました。ジンナーはもともとインドという統一国内でムスリムの権利保護を目指していたのですが、段々と「こりゃ無理だわ」という考えに傾き、ヒンドゥーとムスリムとで別々にやっていった方がいいじゃないかという、二民族論を提唱するようになります。ここでパキスタンという独立構想が現実味を帯びてきます。
しかし、ジンナーの主張は、当然のことながらインド国民会議派からは認められるものではないですし、それどこかイスラム勢力の一部から反発を買い、1943年には刺傷を負うなどジンナー暗殺未遂事件まで起きます。
第二次大戦終戦の年である1945年から46年にかけて、インドで総選挙が実施され、ムスリム連盟とインド国民会議派は、それぞれの割り当て議席枠をキッチリ確保します。選挙によって、インド国内に大きな2グループがあるということがより鮮明に明らかになってしまったわけです。宗主国であるイギリスは、後にパキスタンなるインドの両端エリアをムスリムが仕切り、中央部を国民会議派が仕切り、それを統括する連邦政府があるというギリギリの妥協案を出します。ジンナーは承認しますが、ネルーは中央政府の権限が弱すぎることを危惧し、結局、この案は流れてしまいます。
このような膠着状態において、カルカッタの大虐殺と呼ばれる暴動が起き、数千から数万人のヒンドゥー、ムスリム教徒が殺害されるという惨事になってしまいます。もはやジンナーや国民会議派によって民衆レベルでの対立を抑えきれなくなり、インドとパキスタンは分離して独立することになります。
この時点でジンナーの生命は殆ど尽きかけていました。数年前から結核を患っていたジンナーは、パキスタン独立後のさらなる激務によって健康状態を悪化させ、数ヶ月の保養をとるも病状は改善せず、独立1年後の48年9月に死去します。
このようにインドとパキスタンの産みの苦しみを、その生涯において背負い続け、ほとんど戦死のような壮絶な最後を遂げたジンナーですが、今でもパキスタンにおいては国父、最も偉大な指導者として敬慕されています。紙幣にはジンナーの肖像画が描かれ、カラチの空港はジンナー国際空港と呼ばれています。また、パキスタン国内だけではなく、広くイスラム世界においてジンナーの名は知られており、トルコやイランの大通りにジンナーの名前が使われています。
ジンナーは、インドを二分した”戦犯”であるという見方もあるそうですが、ジンナーはパキスタン構想をやむを得ない次善の策として捉えており、最後の最後まで統一インド構想を捨てることはなかったといいます。それに、今から振り返ってみても、当時のインドの状況は、神様でもない限りクリアすることは出来なかったでしょう。思えば植民地時代は楽であり、ヒンドゥーもムスリムも共に被支配者であり、イギリスに不満をぶつけていれば良かったわけです。しかし、いざ独立となれば、自分達の中での権力配分が重要な問題になります。民主主義における数の論理、数の暴力によってムスリムの権利が侵害されることへの憂慮は、優れた政治家であれば誰しもするでしょう。一部エリートだけではなく広く大衆運動として広めたガンジー、混沌たるインド亜大陸をまとめ上げるために強力な中央政府を求めたネルー、いずれも間違っているわけではないです。
誰も間違ってないのだけど、状況それ自体がどうしようもなかったという。強いて言えば、名もない民衆達がもうちょっとクールに、理性的に動いてくれたらと思うのですが、それまで政治も何も携わったことのない人々が関わろうとすれば、一定数の割合で熱狂的且つ粗暴な方向にいってしまう人々も出てくるでしょう。独立の際のゴタゴタで、多くの人命が犠牲になり、それがまた将来的な憎悪をかきたて今日に連なっていますが、インドという広大な面積と人口を考えたら、この程度で済んだのはまだしもマシだったと思われます。一歩間違えればアフリカの荒れている国のように、国内バトルロイヤルの殺し合いが延々数十年続いたって不思議ではないのですから。
第一次印パ戦争中に国父であるジンナーが死去し、国を束ねるカリスマがいなくなったことで、政局は不安定になります。後を継いだリヤーカト・ハーン首相も1951年に暗殺され、1958年には軍事クーデタまで起きてしまい、アユーブ・ハーンという人が独裁政権を作ります。なお、パキスタンは当初、イギリス国王を元首とする英連邦の自治国家として独立したのですが、この頃(1956年)、共和国として独立しています。
以後、パキスタンは中南米のような展開を余儀なくされます。すなわち、クーデターによる軍事政権と民政移管のくり返しであり、東西冷戦など大国の影響をモロに受けるということです。インドへの軍事対抗措置としてアメリカに接近したパキスタンは、54年にアメリカとの間で相互防衛協定を締結、矢継ぎ早に東南アジアや中東の軍事同盟にも参加します(SEATOとMETO)。
しかし、国際情勢はお天気のように変わりがちです。インドが非同盟主義を貫いていたからこそアメリカと接近したパキスタンですが、今度はインドがアメリカと仲良くなります。発端は1959年のダライ・ラマ亡命で、これでインドと中国の仲が険悪化、62年には国境紛争をめぐってインドと中国の戦争になり、カシミール地方にも飛び火します。戦争は中国の圧勝だったのですが、こうなると「敵の敵は味方」の原理で、反中国であったアメリカとインドの仲がよくなるという理屈です。しかし、インドとアメリカが仲良くされたらパキスタンの安全保障構想は崩れます。そこで、「敵の味方は敵」の原理で、パキスタンはアメリカから中国と仲良くしようとします。問題のカシミールは中国も印中戦争で一枚噛んでおり、中国と連携することでインドとの交渉を容易にしようという腹づもりですね。かくして、58年クーデターで政権をとったアユーブ・ハーンは中国の支援を背景に、再びカシミールでインドと喧嘩をします(1965年第二次印パ戦争)。しかし、これも決着が付かず痛み分け。
そうこうしているうちに、今度は東パキスタンで騒動が起きます。1970年の大型台風(サイクロン)の直撃を受け死者数十万人の被害を出した東パキスタンですが、西パキスタンの災害救助があまりにも少ないことから、翌年の選挙で反西パキスタンの野党が圧勝します。しかし、西パキスタン政府がこれを認めないところから、独立運動が高まり、内戦状態に突入、さらにインドの軍事介入を招いてバングラディッシュ独立戦争=第三次印パ戦争=が起きます。結果的にはインド軍の圧勝で、バングラディッシュは独立します。
一方、国際情勢はまた猫の目のように変わります。反中の立場で手を握ったはずのインドとアメリカですが、インドがアメリカのベトナム戦争批判をしたことから再び仲が悪くなり、インドはソ連と仲良くするようになります。そうするといったんは疎遠になっていたパキスタンとアメリカの仲が戻ります。また、この頃、ニクソン大統領の米中国交というニクソンショックが世界が驚かせており、パキスタンは中国とアメリカと提携し、インドと対峙します。
一方パキスタンの内政ですが、アユーブ・ハーン→ヤヒヤー・ハーンと続いた軍事政権もようやく終焉、1973年にパキスタンは民政移行されます。また、インド、バングラディッシュとの間の交流も再開され、「やれやれ」という雪解けムードになります。が、これも長く続かず、ズルフィカール・ブットーによる人民党の選挙違反をめぐって国内が紛糾、これに乗じてまた軍事クーデタで起きます。政権を奪取したジア・ハックは大統領に就任し、政敵ブットーを処刑、またしても軍事独裁が10年ほど続くことになります。また、イスラム教団体の支持によって政権基盤を固めるために、憲法廃止、イスラム教の祭政一致傾向が進みます。
ジア・ハック軍事政権が10年も続いたのは、カンのいい人は既に洞察しているでしょうが、アメリカの東西冷戦戦略があります。特に79年にソ連のアフガン侵攻によって緊張した国際情勢のもと、アメリカはパキスタンの軍事政権に多大の支援をします。もっとも、アメリカとしてもツライところなんですね。このあたりは過去のエッセイでも書きましたが、なんでソ連がアフガニスタンに侵攻したかといえば、隣のイランでイラン革命が起き、イスラム原理主義が飛び火することをソ連が恐れたからです。イスラム原理主義はアメリカもまた懸念してたところであり、イスラム教への傾斜を深めるハック政権についてはアメリカも支援を中止しようとしていたようです。しかし、先にソ連がアフガンに侵攻してしまったモノだから、イスラムかソ連かどっちが火急の大事かという価値判断の末、対ソ連を優先してハック政権支持をしたようです。
ではなぜハック政権が10年後に終わってしまったか。それはソ連がアフガンから撤退したからです。ゴルバチョフの登場と冷戦終結に世界が動き始めてしまえば、もうアメリカにとってハック政権は用済みです。事実、1988年にハック大統領は飛行機事故でアメリカの都合よく事故死しています。このあまりのタイミングの良さで、CIAの陰謀説がまことしやかに囁かれています。このとき、アメリカ大使も同乗して死亡しており、もし本当にCIAによる暗殺だとしたら、大使もいい面の皮だという気がしますね。
さて、ハック軍事政権のあと、パキスタンは、ハックによって処刑されたブットの娘であるベナズル・ブットが首相になり、民政に戻ります。しかし、平和的な民政ではなかったです。パキスタンは民政化したあとも、核兵器開発やイスラム化を深めますが、これは趣味や主張でやっていたというよりも、全てはライバル・インドの情勢の鏡像現象でしょう。すなわち、インドが核兵器保有を宣言し(中印戦争で負けたのが発端)、さらに核開発を続けていることから、パキスタンも対抗上核兵器を持つ必要があったこと。また、インドにおいて80年以降ヒンドゥー主義が台頭し、88年にはヒンドゥー系の人民党が政権を取るに至るような情勢に対応してのことでしょう。
それに民政移管後の内政ですが、これも10年続くのですが、決して素晴らしい内容ではなく、ベナズル・ブット政権は腐敗がひどく、大統領によって解任され、あとを継いだライバルのナワズ・シャリフ政権は、これまた腐敗がひどく辞任に追い込まれ、選挙で返り咲いたブットが二度目の首相になるも、また性懲りもなく腐敗を起こして、大統領によって解任。再びシャリフが二度目の首相をやりますが、これまた腐敗がひどく、これを批判した軍部のムシャラフを解任をしようとしたため、ムシャラフがクーデターを起こし、三度軍事政権になります。要するに90年代パキスタンの10年間の文民政権は、二人の首相が交互ダブルに首相を勤め、両者一貫して腐敗していたというトホホな状況になります。
このあたりも中南米に似ているのですが、必ずしも文民政権が前で、クーデター軍事政権が悪というものでもないのですね。庶民あがりが多い軍隊の方が、腐敗が少なく、まだしも理想主義的な場合もあるわけです。